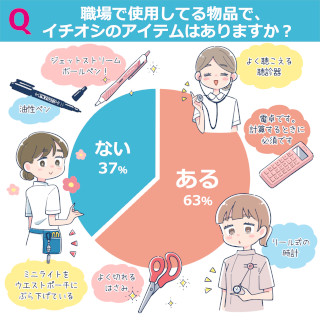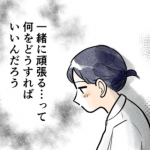「子どもがもうじき小学生。無償化だった保育園と違い、小学校では給食費や学童代に習いごとなど出費が増えそうで不安。でも、小学校時代は貯め時という意見も見聞きする。実際、子育て世帯のみんなはどれくらい貯金しているの?」
今回は、このような不安や悩みを抱えるご家庭のために子育て世帯や30代世帯の平均貯金額をまとめました。

人それぞれとわかってはいても、同じ年代で同じ家族構成の家庭の貯金額は気になるものですよね。この記事で各家庭の平均データを見ながら、ご家庭の貯金額を考えてみてください。
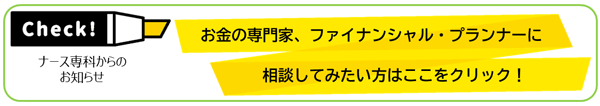
30代はいくら貯めている?30代の平均貯蓄額
まずは、世帯主が30代の世帯の平均貯蓄額を見ていきましょう。
なお、当記事での「貯蓄額」には預貯金から株式・投資信託・債券といった有価証券まで含みます。各家庭の金融資産はどれほどあるのか、参考としてご覧ください。
ここでは厚生労働省の国民生活基礎調査より、世帯主が30代の世帯の平均貯蓄額や平均借入金額を紹介します1)。
<30代世帯の平均貯蓄額>
・世帯主が30代の1世帯あたり平均貯蓄額:530万円
・世帯主が30代の1世帯あたり平均借入金額:1071.1万円
・世帯主が30代の1世帯あたり平均世帯所得:614.8万円
30代の平均貯蓄額は530万円ある一方で、マイホームやマイカーの購入による借入れも1071.1万円あります。同調査では前年度と比べて貯蓄が「減った」と回答している世帯が30.8%、「変わらない」と回答している世帯が37.3%いて、何かと出費が多い30代の現状が窺えます。
※貯蓄額・借入金額は2019年6月末の現在高、世帯所得は2018年1月1日~12月31年の1年間の所得
子育て世帯はいくら貯めている?平均貯蓄額
一方、子育て世帯の貯金額はいくらあるのでしょうか。
先ほど紹介した厚生労働省の「国民生活基礎調査」より、「児童のいる世帯」の貯蓄平均をご紹介します2)。
<児童のいる世帯の平均貯蓄額>
・児童のいる世帯の1世帯あたり平均貯蓄額:723.8万円
・児童のいる世帯の1世帯あたり平均借入金額:1119.7万円
・児童のいる世帯の1世帯あたり平均世帯所得:745.9万円
※貯蓄額・借入金額は2019年6月末の現在高、世帯所得は2018年1月1日~12月31年の1年間の所得
何かと出費が多い「30代」という枠を省き「児童のいる世帯」に絞ると、平均貯蓄額は700万円を超えています。一方で、児童のいる世帯のうち11.6%の世帯には貯蓄がないという調査結果もあります。また、貯蓄がある世帯の半数は貯蓄額が700万円以下です。平均貯蓄額だけ見ると多くの貯蓄額があるように感じますが、貯蓄額の多い世帯が平均を押し上げている可能性もあります(表1)。
表1 児童のいる世帯の貯蓄額とその割合3) (2019年)
| 総数 | 100.0(%) |
|---|---|
| 貯蓄がない | 11.6 |
| 貯蓄がある | 84.4 |
| 50万円未満 | 4.3 |
| 50~100 | 4.9 |
| 100~200 | 10.1 |
| 200~300 | 8.1 |
| 300~400 | 7.7 |
| 400~500 | 4.4 |
| 500~700 | 10.6 |
| 700~1000 | 8.1 |
| 1000~1500 | 8.7 |
| 1500~2000 | 3.8 |
| 2000~3000 | 4.6 |
| 3000万円以上 | 3.9 |
| 貯蓄あり額不詳 | 5.3 |
| 不 詳 | 4.0 |
| 1世帯あたり平均貯蓄額 | 723.8万円 |
30代 年収別の平均貯蓄額と中央値
先ほどは「30代」や「子育て世帯」という大きなくくりで平均貯蓄額を見てきました。
ここからは一歩踏み込んで、年収ごとの平均貯蓄額や貯蓄の中央値をご紹介します。中央値とは、あるデータを小さい数値から大きい数値まで順番に並べた場合、ちょうど中央にくる値のことです。
平均値は一部の人の貯蓄額に数値が左右される傾向があります。たとえばデータの中に一人貯蓄が5,000万円超ある人がいると、その一人によって平均額が押し上げられてしまう可能性があるのです。そこで平均値とあわせて中央値もあわせて見ることでよりリアルな「中間層」の貯蓄額の実態が見えてくるのではないでしょうか。
ここでは金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査「2人以上世帯調査」」より、世帯主が30代の世帯の平均貯蓄額と中央値を年収別にまとめました(表2)。
表2 30代の世帯の年収別平均貯蓄額・中央値4)
| 年数 | 平均貯蓄額 | 中央値 |
|---|---|---|
| 300万円未満 | 187万円 | 55万円 |
| 300~500万円未満 | 337万円 | 250万円 |
| 500~750万円未満 | 721万円 | 550万円 |
| 750~1,000万円未満 | 1,338万円 | 1,318万円 |
| 1,000~1,200万円未満 | 923万円 | 850万円 |
| 1,200万円以上 | 905万円 | 905万円 |
※上記の「年収」は、就業に伴う収入、年金、不動産賃貸収入、利息収入などの税引き後収入を指す。
年収ごとの貯蓄額を見ていくと、意外なことに750~1,000万円未満の世帯がもっとも貯蓄額が多い結果となっています。また、年収が上がるにつれて平均値と中央値のギャップはなくなっていく傾向があります。
まとめ:結局、30代で子持ち世帯はいくら用意すればいいの?
ご紹介してきた30代や子育て世帯の平均貯蓄額を、改めて並べると以下のとおりです。
・世帯主が30代の世帯:平均貯蓄額530万円
・子どもがいる世帯:平均貯蓄額723.8万円
・世帯年収500万円~750万円の30代世帯:平均貯蓄額721万円 貯蓄の中央値550万円
もちろん、平均値や中央値だけでは個別の家庭状況はわかりませんし、平均値=貯蓄必要額とは言えません。各家庭で必要な貯蓄額やマイホームやマイカーの購入状況、子どもの人数などで大きく変わってきます。平均値や中央値はあくまで一つの目安として、各家庭で必要な貯蓄額を考えることが大切です。
なお、子どもの教育費の必要貯蓄額については、こちらの記事で詳しく解説しています。あわせて参考にしてみてください。
<関連記事>
教育費はいつまでに・いくら用意すべき? 平均費用と具体的な貯め方をシミュレーション
https://square.nurse-senka.jp/articles/150008710
繰り返しますが、必要な貯蓄額は各家庭によって異なります。今回ご紹介した平均値や教育費の記事を参考にしつつも、個別の状況についてはお金の専門かであるFPに相談することをおすすめします。FPであれば、各家庭のライフプランにあわせた必要貯蓄額をシミュレーションしてくれるはずです。「30代子育て世帯」という軸ではなく、「我が家の必要貯蓄額」をしっかり計算したいという人は、FPに相談してみてくださいね。
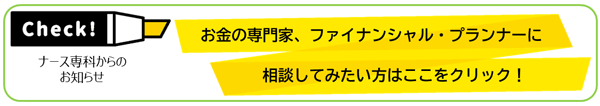
出 典
1)厚生労働省:2019年 国民生活基礎調査の概況.Ⅱ 各種世帯の所得等の状況、p.10、p.13.
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa19/dl/03.pdf(2022年3月8日閲覧)
2) 厚生労働省:2019年 国民生活基礎調査の概況.p.9、p.12.
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa19/index.html(2022年3月8日閲覧)
3) 厚生労働省:2019年 国民生活基礎調査の概況.Ⅱ 各種世帯の所得等の状況、p.10、p.13.
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa19/dl/03.pdf(2022年3月8日閲覧)
4) 金融広報中央委員会:家計の金融行動に関する世論調査.2人以上世帯調査(令和2年)、シート1.
https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/yoron/futari/2020/20crossf001.html(2022年3月8日閲覧)
この記事を書いたのは
服部 椿
金融代理店での勤務経験と自身の投資経験を活かしたマネーコラムを多数執筆中。
子育て中のママFPでもあり、子育て世帯向けの資産形成、ライフプラン記事の執筆が得意。
保有資格:2級ファイナンシャル・プランニング技能士
記事監修:株式会社ファーストプレイス
イラスト:tetekun
Twitter:https://twitter.com/tete_ponyo
バナー素材:イラストAC
関連記事
-
 【イクメンクエスト】看護師ママはパパの協力が不可欠!看護師ママが考えた「旦那をイクメンに育てる方法」看護師という仕事は、病気や生命に関わるため、緊張を保って仕事をしなければいけません。仕事が終わるとヘトヘト、なんてことも多いと思います。さらに夜勤勤務も…となると、もうパパと協力して育児をしないと、毎日が回りません。 でも、パパと上手...エッセイ2022/02/16
【イクメンクエスト】看護師ママはパパの協力が不可欠!看護師ママが考えた「旦那をイクメンに育てる方法」看護師という仕事は、病気や生命に関わるため、緊張を保って仕事をしなければいけません。仕事が終わるとヘトヘト、なんてことも多いと思います。さらに夜勤勤務も…となると、もうパパと協力して育児をしないと、毎日が回りません。 でも、パパと上手...エッセイ2022/02/16 -
 【看護職限定・無料】福島復興プロジェクトバスツアー開催!被災地であなたのスキルを存分に発揮してみませんか?【先着20名】医療で福島を支える!復興プロジェクトに参加しませんか? 「福島復興プロジェクト」とは、経済産業省から委託を受けた「福島求人支援チーム」が主催するプロジェクト。「伝統を守り続けたい」「町を活気づけたい」「ふるさとの再生に貢献したい」――福島...エッセイ2022/02/16
【看護職限定・無料】福島復興プロジェクトバスツアー開催!被災地であなたのスキルを存分に発揮してみませんか?【先着20名】医療で福島を支える!復興プロジェクトに参加しませんか? 「福島復興プロジェクト」とは、経済産業省から委託を受けた「福島求人支援チーム」が主催するプロジェクト。「伝統を守り続けたい」「町を活気づけたい」「ふるさとの再生に貢献したい」――福島...エッセイ2022/02/16 -
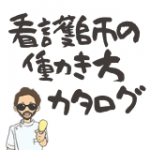 乳児院看護師|上田茜さん虐待をなくしたい!大学病院でのキャリアを悩みながらも、己の心に従って乳児院へ進んだ上田 茜さん 看護師のさまざまな働き方を紹介するコーナー。第7回は大学病院で順当なキャリアを築きながらも、自分がやりたかったこと、経験したことを...エッセイ2022/02/16
乳児院看護師|上田茜さん虐待をなくしたい!大学病院でのキャリアを悩みながらも、己の心に従って乳児院へ進んだ上田 茜さん 看護師のさまざまな働き方を紹介するコーナー。第7回は大学病院で順当なキャリアを築きながらも、自分がやりたかったこと、経験したことを...エッセイ2022/02/16 -
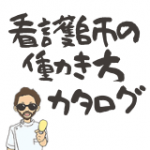 保育園看護師|谷川祐美さん保育園で園児やスタッフたちの健康管理にあたる谷川祐美さん 看護師のさまざまな働き方を紹介するコーナー。第6回は、大学病院や中規模病院の消化器外科で経験を積んだのち、保育園看護師に転職した谷川祐美さん。現在5年目の谷川さんに、こ...エッセイ2022/02/16
保育園看護師|谷川祐美さん保育園で園児やスタッフたちの健康管理にあたる谷川祐美さん 看護師のさまざまな働き方を紹介するコーナー。第6回は、大学病院や中規模病院の消化器外科で経験を積んだのち、保育園看護師に転職した谷川祐美さん。現在5年目の谷川さんに、こ...エッセイ2022/02/16 -
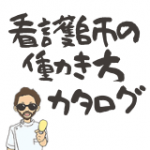 精神科訪問看護師|谷川寛郎さん精神科嫌いから精神科訪問看護師になった谷川寛郎さん 看護師の働き方を紹介するコーナー。第5回は、外科やオペ室を経験し、精神科の患者さんが苦手だったにもかかわらず、現在はその魅力にハマり精神科訪問看護師になった谷川寛郎さん。18年目...エッセイ2022/02/16
精神科訪問看護師|谷川寛郎さん精神科嫌いから精神科訪問看護師になった谷川寛郎さん 看護師の働き方を紹介するコーナー。第5回は、外科やオペ室を経験し、精神科の患者さんが苦手だったにもかかわらず、現在はその魅力にハマり精神科訪問看護師になった谷川寛郎さん。18年目...エッセイ2022/02/16