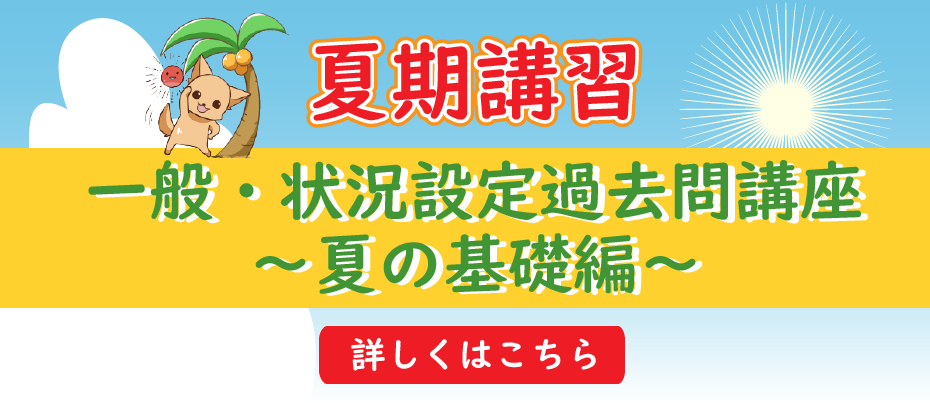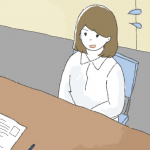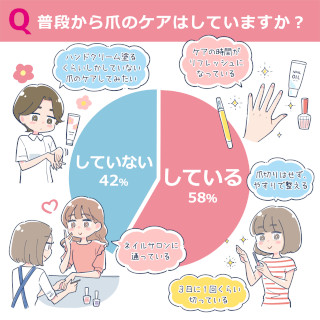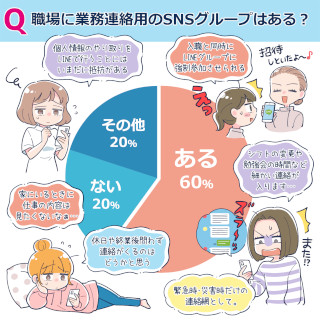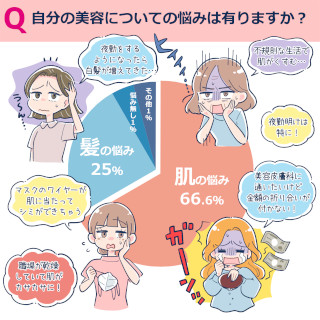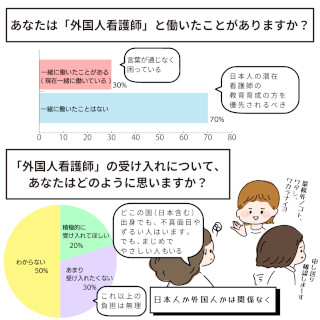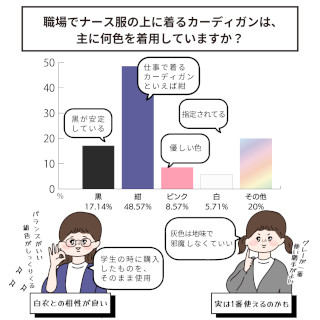こんにちは、さわ研究所です!
今回は【一般・状況設定問題】にフォーカスし、近年のトレンド分析から第115回の対策のポイントまでをお届けします。さらに、オリジナル予想問題とその解説講義動画を用意しました。ぜひチェックしてみてください。
目次
第114回看護師国家試験の一般・状況設定問題はどうだった?
ここでは、第114回の一般問題および状況設定問題を振り返り、印象に残った出題例をいくつか紹介します。第114回一般問題の振り返り
第114回の一般問題で注目すべき科目は「人体の構造と機能」です。さわ研究所が集計した正答率によると、出題された9問のうち6問が50%以下、1問が50%台、2問が60%台と、全体的に正答率が低くなっています。特に、例年受験直前に「もっと学習しておけばよかった」という声を多く聞くのが「解剖生理」です。早い段階で解剖生理の理解を深めておきましょう。また、第114回では10年以上前に出題された内容が再度出題されました。午前No.85の肝細胞癌の問題です。こちらは第96回午後No.22の問題とほぼ同じ内容ですが、正答率が10%と非常に低い結果でした。
以下が該当する2つの問題です。
問題:第114回問題:肝細胞癌で正しいのはどれか。2つ選べ。(午前No.85)
- 早期から黄疸が出現する。
- 原発性肝癌の中で最も頻度が高い。
- 診断に腹部超音波検査が用いられる。
- 特異性の高い腫瘍マーカーはCEAである。
- 肝内胆管の細胞が腫瘍化して発生する癌である。
問題:第96回問題:肝細胞癌で正しいのはどれか。(午後No.22)
- 早期から黄疸が出現する。
- 肝硬変を併発していることが多い。
- 特異性の高い腫瘍マーカーはCEAである。
- 我が国ではB型肝炎ウイルスに起因するものが最も多い。
第114回問題の解答は2と3、第96回問題の解答は2です。
第96回は古い問題ですが、さわ研究所の黒本に載っていたので、こちらを使っていた受験生は対策できていたのではないでしょうか。一方で、国家試験対策として過去問題を解いていなかった人や、ここ数年で出題された問題しか解いていなかった人にとっては、難しかったようです。
第114回状況設定問題の振り返り
第114回の状況設定問題を振り返ると、5肢択二の問題の正答率が非常に低く、受験生が苦戦したことがうかがえます。その一例がこちらの問題です。
第114回問題:次の文を読み112~114の問いに答えよ。
Aさん(36歳、経産婦)は、夫(35歳)、男児(3歳)と3人で暮らしている。妊娠、分娩経過は順調で、妊娠39週5日で3,200gの女児を経腟分娩で出産した。1分後のApgar〈アプガー〉スコア9点、5分後のApgar〈アプガー〉スコア10点であった。
産褥1日、Aさんの子宮底は臍下2横指、硬度良好、悪露は赤色であった。「1人目の出産後よりもお腹が痛くて眠れませんでした」と看護師に話す。
このときのAさんへの説明で適切なのはどれか。2つ選べ。(午前No.112)
- 「痛み止めは使用できません」
- 「授乳をすると痛みが和らぎます」
- 「経産婦のほうが痛みを強く感じます」
- 「産後5日くらいまで痛みは続きます」
- 「子宮が元の大きさに戻るための痛みです」
実習で経産婦を受けもっていないと、初産婦よりも経産婦のほうに痛みが強く出るということが分からなかったかもしれません。これは、子宮を風船に例えて考えると分かりやすくなります。初めて膨らませた風船が縮むときよりも、一度しぼませた風船を再び膨らませたほうが、縮むときに力が必要になることを連想できると、正しい選択肢を選べるでしょう。
なお、過去の一般問題では次のような問題が出題されていました。
第97回問題:正常分娩をした初産婦。産褥5日の子宮復古状態で正常なのはどれか。(午前No.136)
- 後陣痛がある。
- 赤色悪露がみられる。
- 子宮底の高さが臍と恥骨の中央である。
- 子宮の硬さがゴムまり状である。
このように状況設定問題だけではなく、一般問題の過去問題も活用して知識をつけることや、周辺知識をあわせて確認することが状況設定問題の得点アップにつながります。なお、この過去問題の正解は3です。
そのほかに印象に残った問題として、第114回では心筋梗塞の患者さんの離床中止の判断理由に関する問題(午後No.95)が出題されました。これは、病態の理解と、ケアをする際に看護師が判断する指標の解釈とが求められる高レベルな複合問題です。
これからの国家試験でも、覚えた知識を繋げて正解を導き出す力が必要な問題が出題されると予想されます。国家試験対策で問題を解く際には「なぜこの選択肢が最も適切なのか」と「なぜそのほかの選択肢は適切ではないのか」を、自分の言葉で説明できるように取り組みましょう。
【一般・状況設定問題】第112〜114回の出題傾向は?
近年の国家試験では、単に知識を問われる問題ではなく、“知識と情報をもとに考えて判断する力”が求められている問題が多くみられます。例えば、国家試験で心不全の患者さんの状態として「体重増加、下腿浮腫、SpO₂ 91%、起坐呼吸、頸静脈怒張」と記載されていたら「心不全の悪化だな」と気づけるでしょうか。さらに、そこから「肺うっ血は進行している?」「体位の工夫が必要?」「酸素投与の評価は?」と、繋げて考えられる力をつけておくことが必要です。
また第114回では、糖尿病患者さんの在宅での自己管理の問題(午後No.41)や、一人暮らしの高齢者に提供する社会資源の問題(午後No.114)など、“生活環境”や“患者さんの背景”を踏まえて解答しなければならない問題も出題されました。
このような問題も単なる暗記のみでは正解にたどり着けません。例えば、家族などの支援がなく1人で生活する高齢者と、家族などの支援がある高齢者では、提供する社会資源の情報も異なります。これらの問題に対応するためには、患者さんに寄り添った看護の視点をもつことが必要です。
【一般・状況設定問題】第115回の対策のポイント
第115回でも、近年と同様、身につけた知識とその場の状況を組み合わせて答えを導く“応用力”や“展開力”が求められると考えられます。このような力を養うためには、実習での経験が最も効果的です。患者さんの状態や場面に応じて考え、判断し、行動するといった実践的な積み重ねが国家試験でも活きてきます。また、座学では多くの過去問題に触れ、必要な知識だけでなくそれらを繋げて考える力を身につけましょう。過去問題を繰り返し解くことで、知らず知らずのうちに知識が定着し「この問い方は以前みたことがある」や「この疾患に関する問題ではあのキーワードが出ることが多い」などのように、重要なポイントも自然と頭に残るようになります。また、応用力や展開力を身につけることにも繋がるため、できる限り早く過去問題を解き進めましょう。
【一般問題】第115回の予想問題にチャレンジ!
第115回の一般問題で出題が予想される問題を3つ紹介します。振り返りに役立つ解説講義動画も用意していますので、ぜひチャレンジしてみてください。問題1:脳神経の中で副交感神経を含むのはどれか。
- 滑車神経
- 三叉神経
- 内耳神経
- 舌咽神経
- 舌下神経
解答
4
問題1の解説講義はこちら!
問題2:高尿酸血症で正しいのはどれか。
- 痛風結節は痛みを伴う。
- 痛風発作は過労で誘発される。
- 治療のために激しい運動を促す。
- 血清尿酸値が5.0mg/dL以上をいう。
解答
2
問題2の解説講義はこちら!
問題3:Aさんは2型糖尿病と診断され食事指導を受けている。しかし、食事指導の内容を守れておらず、体重も前回受診時より増加している。看護師がAさんに食事について話を聞くと「友人がランチに誘ってくるから食事指導が守れない」と訴えてきた。Aさんにはたらいている防衛機制はどれか。
- 昇華
- 退行
- 合理化
- 反動形成
- おきかえ
解答
3
問題3の解説講義はこちら!
一般・状況設定の対策には“考える力”が不可欠!
近年の一般・状況設定問題は、知識だけではなく、それを活用した応用力や展開力、つまり“知識を繋げて考える力”が求められます。このような力を養うためには、実習での経験から学ぶことと、過去問題を用いた学習を中心として継続的に学習することが大切です。まずは必要な知識を身につけるためにできる限り早く国家試験対策を始め、日々の学習のなかで“考える力”を育てていきましょう。
今からできる!おすすめの国家試験対策
①まずは解剖生理の学習を!
解剖生理が分かれば病態生理が理解できる。病態生理が理解できれば、看護に繋がる。
→この繋がりを意識しつつ、まずはこれまでに身につけた解剖生理の知識を整理しましょう。
②実習経験とリンクさせる
国家試験対策では、実習で受けもった患者さんと同じ疾患の過去問題から取り組んでいくこともおすすめです。「あの患者さんと同じ疾患だから、この場合は……」
「このケアにはどんな根拠があったかな?」
→このように経験と知識を組み合わせると理解しやすくなり、さまざまな情報から看護に繋げられるようになります。
③理由とセットで解答するクセづけをする
「これが正解っぽい」ではなく、「なぜこの選択肢が正解なのか」や「ほかの選択肢が誤りである理由は何か」を自分の言葉で説明する習慣をつけましょう。この習慣をつけることで得点アップに繋がります。