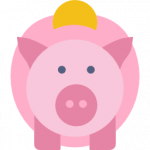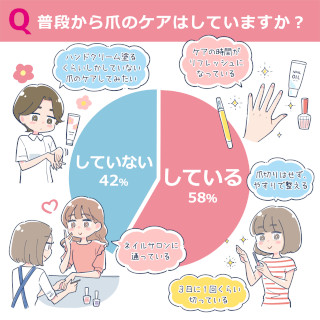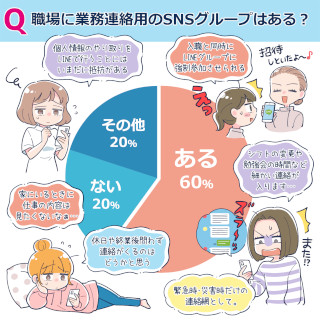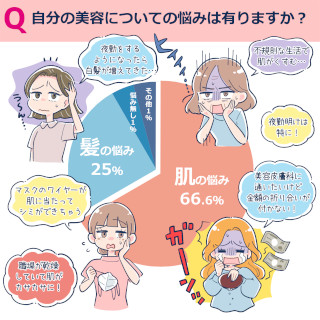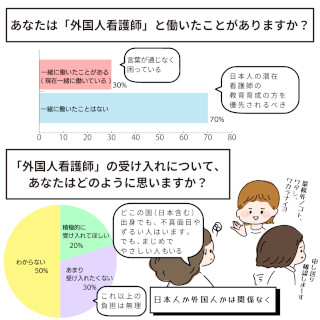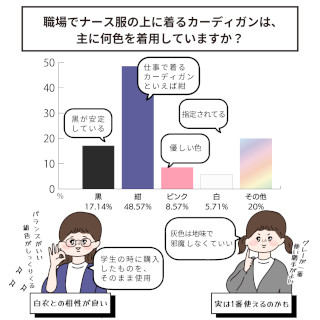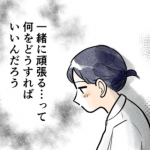2024年11月4日からスタートした1日3問国試ドリルは、月~金で1日3問ずつ配信しています。
このページでは、1日3問国試ドリルで配信した問題のうち、「必修問題」に該当する問題と解答・解説を掲載します。振り返りにぜひ活用してください。【※毎週更新予定】
第1問:健康な成人の白血球の中に占める割合が高いのはどれか。
- 単球
- 好酸球
- 好中球
- リンパ球
解答・解説
1.(×)白血球のうち3~8%が単球である。
2.(×)白血球のうち2~4%が好酸球である。
3.(〇)白血球のうち60~70%が好中球で、最も割合が高い。
4.(×)白血球のうち20~40%がリンパ球で、好中球に次いで割合が高い。
第112回(2023年)
第2問:深部体温に最も近いのはどれか。
- 腋窩温
- 口腔温
- 鼓膜温
- 直腸温
解答・解説
1.(×)深部体温は核温とも呼ばれ、外界の温度の影響を受けない身体の深部の温度である。鼓膜温、直腸温、膀胱温などがあり、最も高いのが直腸温である。
2.(×)
3.(×)
4.(〇)
第111回(2022年)
第3問:器質的変化で嚥下障害が出現する疾患はどれか。
- 食道癌
- 脳血管疾患
- 筋強直性ジストロフィー
- Guillain-Barre(ギランバレー)症候群
解答・解説
1.(〇)器質的変化とは感染や炎症、血管障害などによって細胞や組織が破壊されたり変化したりすることをいう。嚥下障害が生じる器質的変化には、先天奇形や咽頭や喉頭、食道癌、外傷などがある。
2.(×)脳血管疾患は、仮性球麻痺・球麻痺によって運動障害性嚥下障害が出現することがある。
3.(×)筋強直性ジストロフィーは、嚥下に関わる筋肉の筋力低下や萎縮によって運動障害性嚥下障害が出現することがある。
4.(×)ギランバレー症候群は脳神経障害を生じ、運動障害性嚥下障害が出現することがある。
第113回(2024年)
第4問:滅菌物の取り扱いで正しいのはどれか。
- 鉗子の先端は水平より高く保つ。
- 鑷子の先端を閉じた状態で取り出す。
- 滅菌パックはハサミを用いて開封する。
- 滅菌包みは布の内側の端を手でつまんで開く。
解答・解説
1.(×) 鉗子の先端は必ず水平より低く保つ。
2.(〇)鑷子の先端を閉じた状態で取り出す。
3.(×) 滅菌パックは開封する側を上にして、両手で左右に開く。ハサミは使用しない。
4.(×) 滅菌包みは内側が清潔なため、布の外側の端を手でつまんで開く。
第109回(2020年)
第5問:ハヴィガーストR.J.が提唱する老年期の発達課題はどれか。
- 子どもを育てる。
- 退職と収入の減少に適応する。
- 社会的責任をともなう行動を望んでなしとげる。
- 男性あるいは女性としての社会的役割を獲得する。
解答・解説
1.(×) 子どもの養育は壮年初期の発達課題である。
2.(〇)隠退と減少した収入に適応することは、老年期の発達課題である。
3.(×) 社会的責任をともなう行動を望んでなしとげることは、青年期の発達課題である。
4.(×) 男性あるいは女性としての社会的役割を獲得することは、青年期の発達課題である。
第110回(2021年)
第6問:自力での摂取が困難な成人患者の食事介助で適切なのはどれか。
- 水分の少ない食べ物を準備する。
- 時間をかけずに次々と食物を口に入れる。
- 患者に食事内容が見える位置に食器を配置する。
- 患者の下顎が上がるよう高い位置からスプーンを操作する。
解答・解説
1.(×) 水分が少ないと嚥下しにくいため、不適切である。
2. (×)患者のペースに合わせる必要があるため、不適切である。
3.(〇)食事内容を見えるようにすることで、食事への意欲が増すため適切である。
4.(×) 顎を上がった状態では誤嚥しやすいため、不適切である。
第110回(2021年)
第7問:脳死の状態はどれか。
- 縮瞳がある。
- 脳波で徐波がみられる。
- 自発呼吸は停止している。
- 痛み刺激で逃避反応がある。
解答・解説
1.(×)瞳孔が固定し、左右とも直径4mm以上に散大する。
2.(×)脳波は検出されず、平坦になる。
3.(〇)自発呼吸は消失する。
4.(×)痛み刺激に対して反応しない。痛み刺激は、顔面への滅菌針、滅菌した安全ピンなどを使用した刺激か、眼窩切痕部への指での強い圧迫刺激を行う。
第113回(2024年)
第8問: 成人で1日の尿量が100mL以下の状態を示すのはどれか。
- 希尿
- 頻尿
- 乏尿
- 無尿
解答・解説
1.(×)希尿は排尿回数が少ない状態を指す。
2.(×)頻尿は排尿回数が多い状態を指す。昼間頻尿は日中覚醒時の排尿回数が8回以上、夜間頻尿は夜間就眠中に覚醒しての排尿が2回以上をいう。
3.(×)乏尿は1日尿量が400ml以下の場合を指す。
4.(〇)無尿は1日尿量が100ml以下の場合を指す。
第109回(2020年)
第9問:グリセリン浣腸を準備する際の浣腸液の温度で適切なのはどれか。
- 20℃
- 30℃
- 40℃
- 50℃
解答・解説
1.(×)浣腸液温は、直腸温に近い約40℃(40~41℃)が適切である。高温(43℃以上)では腸粘膜に炎症を起こし、低温では腸壁の毛細血管が収縮して血圧を上昇させたり、寒気を起こしたりする場合がある。
2.(×)
3.(〇)
4.(×)
第112回(2023年)
第10問: 無菌操作が必要なのはどれか。
- 浣腸
- 気管内吸引
- 口腔内吸引
- 経鼻胃管挿入
解答・解説
1.(×)肛門や大腸には腸内細菌が常在しているため、無菌操作の必要はない。
2.(〇)気管は無菌が保たれている場所である。気管内への細菌の侵入は、肺炎などの感染症を引き起こすため、気管内吸引の際には無菌操作が必要となる。
3.(×)上気道(鼻腔、口腔、咽頭、喉頭)は常在菌が存在しているため、口腔内吸引で無菌操作の必要はない。
4.(×)経鼻胃管挿入は、チューブを常在菌の存在する鼻腔から胃まで挿入するため、無菌操作の必要はない。
第113回(2024年)
第11問: 指定訪問看護ステーションには常勤換算で( )人以上の看護職員を配置することが定められている。 ( )に入るのはどれか。
- 1.0
- 1.5
- 2.0
- 2.5
解答・解説
1.(×)指定訪問看護ステーションには常勤換算で2.5人以上の看護職員を配置することが定められている。
2.(×)
3.(×)
4.(〇)
第111回(2022年)
第12問: 薬物の吸収速度が最も速いのはどれか。
- 経口投与
- 筋肉内注射
- 静脈内注射
- 直腸内投与
解答・解説
1.(×)薬物の吸収速度は、静脈内注射→筋肉内注射→直腸内投与→皮下注射→経口投与の順で速い。
2.(×)
3.(〇)
4.(×)
第112回(2023年)