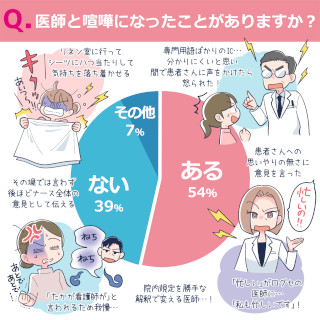胎児期から新生児、小児、思春期を経て、新たな生命を生み育てる成人世代までのリプロダクションサイクルにある人々を対象に、総合的かつ継続的な医療(=成育医療)を提供してきた国立成育医療センター。本年4月に、独立行政法人 国立成育医療研究センター病院として新たな一歩を踏み出した、同院の副院長であり看護部長、石井由美子さんにお聞きします。
外国映画に出ていた「白衣の天使」に憧れて
──石井さんが看護師を目指されたきっかけは何ですか。
看護師になろうと思ったのは、幼いときにテレビで見た外国映画に出ていた「白衣の天使」への憧れからです。それと併せもっていたのが「京都」への憧れ。その両方をいっぺんに叶えるために、京都の看護学校を探したのがきっかけで、高校まで過ごした栃木を離れ、国立京都病院付属看護助産学校に進むことになりました。
そんな動機ですから、入学後は勉強の大変さにもうビックリで、実習が始まると、事前勉強に、記録に、レポートに……と本当にきつかったですね(笑)。そのなかで休日を利用しては京都の街を散策することが、京都の生活での楽しみでした。
当初は卒業後もそのまま京都に残ろうと思っていたのですが、ホームシックになったこともあって、実家から約1時間で通える国立高崎病院(現・高崎総合医療センター)に入職を決めました。小児一般領域でしたが、希望していた小児科に配属され、ここから看護師歴の半分近くかかわることになる小児看護をスタートさせたのです。
外科病棟で受けたカルチャーショック
──高崎病院では、印象的な出来事や影響を受けた人物との出会いはありましたか。
小児科病棟で4年あまり勤務した後、外科病棟へ異動になったのですが、そこでは専門用語や略語が飛び交い、何を言っているのかさっぱりわからず、カルチャーショックを受けましたね。最初の頃は男性ばかりの6人部屋に入ることすらできなかったんですよ(笑)。
数カ月後には小児科とは違った看護の楽しさも理解できるようになりましたが、あの異動は衝撃的な出来事でした。また、外科病棟ではがんで亡くなられる患者さんも多く、自分が何もできない無力感でつらい思いもしました。そんなとき出会ったのが、聖母病院のシスター・寺本松野さんの言葉でした。
「看護師は女優よ」が病棟でブームに
――シスター・寺本松野さんは、当時の看護師の憧れですね。
寺本さんは「あなたがそこにいるだけで看護になる。そういう看護が大切」と説いていたのです。とても胸に響きました。患者さんから、「つらいから、私のそばにいてほしい」と言われる信頼関係を築ける看護をしたいと、思いを強くしたことを覚えています。
ちょうど同じ頃だったでしょうか、同じ病棟の看護師がある講演会で「看護師は女優だ」という話を聞いてきたんです。「看護師はどんなにつらくても、嫌いな患者さんでも常に笑顔で接するべき。だから、看護師は女優である」というんですね。
病棟内で「私たちは女優よ!」という言葉がブームになったのですが、私は違うと思いました。私は看護師を演じるのではなく、素の自分が患者さんと一緒に笑ったり泣いたりできる関係をつくりたい。嫌と言うことのできる関係をつくることが大事だと思ったんですね。それには、やはり患者さんから信頼されることが第一です。この2つの言葉は、今日まで看護師として働くうえでの礎になりました。
優秀な看護師がいるのに全体に行き届いていない
──石井さんは小児看護に長くかかわり、小児医療の高度専門医療施設の看護部長に就任されました。看護部の印象はいかがでしたか?
一昨年、甥の嫁のお産で面会に訪れたことがあったのですが、まさか自分がこの病院の看護部長になるとは思いもしませんでした(笑)。
研究所を併設し、高度先進医療を行い、その情報を発信する施設であり、建物や設備も素晴らしいのですが、着任してみると全く問題がないわけではありませんでした。専門性の高い優秀な看護師がいるのですが、その人たちの影響が看護部内の隅々にまで浸透せず、全体のレベルアップにつながっていない印象を受けたのです。
また、小児看護への希望を抱いて全国から看護師が応募してきますが、新人・ベテランにかかわらず退職やバーンアウトが多いのも気になりました。可愛い子どもたちが病気を治し、元気に退院していく小児病院を想像して入職したら、現実は全国から基礎疾患や先天性疾患のある重症度の高い子どもたちが集まっていた──。
中には人工呼吸器を装着した子どもを前にパニックになったり、業務に忙殺された結果、病棟の前にくると動悸がして入れない新人看護師もいました。重症度の高さと看護業務の忙しさは比例するものですが、理想と現実とのギャップに打ちのめされ、看護の面白さに気づけないまま疲弊してしまうのはとても残念なことです。
――高度な専門医療施設ならではの悩みを抱えるスタッフがいたのでしょうね。
40代の看護師が、「自分の居場所はここにはない」という理由で退職を申し出てきたこともあります。地道に20年余やってきたのに、新人がどんどん入ってきて、自分の居場所がなくなると感じたのでしょう。言葉少ない彼女に「あなたの洗髪と新人の洗髪は違うんじゃないの」と声をかけたら、ぼろぼろと泣き出してしまった。専門性や新しい知識に心の比重がかかりすぎて、いろいろなタイプの看護師がいてよいことも、この病院にはあなたが必要なんだというメッセージも、うまくフィードバックされなかったのでしょうね。
当院は高度先駆的医療を提供する施設として専門分野の看護師が活躍するイメージが強く、実際それを目指す看護師も多くいますが、一方で地道にスキルを磨いてきた看護師の居場所がなくなるような二極化が進んでいるように思えるのです。双方がうまく混ざり合い、全体を底上げできればと思いますが、それには一人ひとりと丁寧にかかわることがとても大事なのだと痛感しています。
次のページは、途中退職者ゼロをめざす石井さんの取り組みについてです。