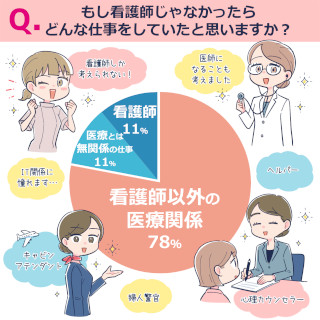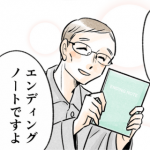2024年11月4日からスタートした1日3問国試ドリルは、月~金で1日3問ずつ配信しています。
このページでは、1日3問国試ドリルで配信した問題のうち、「母性看護学」に該当する問題と解答・解説を掲載します。振り返りにぜひ活用してください。【※毎週更新予定】
第1問:正常に経過している妊娠36週の妊婦が、次に妊婦健康診査を受診する時期として推奨されるのはどれか。
- 4週後
- 3週後
- 2週後
- 1週後
解答・解説
1.(×) 妊婦健診の受診頻度は、妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週以後出産までは1週間に1回となる。妊娠36週であれば、1週間後になる。
2.(×)
3.(×)
4.(〇)
第109回(2020年)
第2問:正常な分娩経過はどれか。
- 骨盤入口部に児頭が進入する際、児の頤部が胸壁に近づく。
- 骨盤出口部に達した時点で、児頭の矢状縫合は母体の骨盤の横径に一致する。
- 児頭娩出後、胎児は肩の長軸が骨盤出口部の横径に一致するよう回旋する。
- 児頭が発露したころに胎盤が剝離する。
解答・解説
1.(〇)骨盤入口部は狭いため、児は頤部(おとがいぶ:あご先のこと)を胸に引き付けることで最も頭の幅が小さい状態となり、骨盤への児頭進入が可能になる。
2.(×)骨盤出口部に達した時点で、児頭の矢状縫合は母体の骨盤の縦径に一致する。
3.(×)児頭娩出後、胎児は肩の長軸が骨盤出口部の縦径に一致するよう回旋する。
4.(×)胎盤の剥離は胎児の娩出後である。
第112回(2023年)
第3問:順調に分娩が進行している妊娠40週0日の初産婦から「腟から水っぽいものが流れ、下着が濡れた」とナースコールがあった。看護師が流出したものを確認すると、量は少量で、羊水特有の臭いを認めた。このときの産婦への対応で優先度が高いのはどれか。
- バイタルサインを測定する。
- 胎児心拍数を確認する。
- 食事摂取を勧める
- 更衣を促す。
解答・解説
1.(×) 破水時には、胎児心拍の確認が最も優先度が高い。もし、羊水の性状が血性であったり、悪臭を伴ったりする場合には産婦のバイタルサイン測定も急がれる。
2.(〇)破水時には、胎児心拍の確認が最も優先度が高い。
3.(×)破水直後に食事摂取を勧めることは優先度として低い。
4.(×)胎児心拍を確認後、更衣を促す。
第113回(2024年)
第4問:妊娠の初期と後期のどちらの時期にも起こるマイナートラブルはどれか。
- 下肢静脈瘤
- 搔痒感
- つわり
- 頻尿
解答・解説
1.(×) 下肢静脈瘤は、妊娠後期におこりやすい。
2.(×) 掻痒感は妊娠全期を通しておこりやすい。
3.(×) つわりは妊娠5週頃~妊娠16週頃までみられることが多い。
4.(〇)妊娠初期は子宮の増大に伴う膀胱への刺激によって、妊娠後期には児頭下降による膀胱の圧迫が頻尿をひきおこす。
第110回(2021年)
第5問:避妊法について適切なのはどれか。
- 経口避妊薬は排卵を抑制する。
- コンドーム法の避妊効果は99%以上である。
- 基礎体温法は月経が不順な女性に有用である。
- 子宮内避妊器具(IUD)は性交のたびに挿入が必要である。
解答・解説
1.(〇) 経口避妊薬は、視床下部からのゴナドトロピン放出ホルモン(GnRH)の分泌と下垂体からのFSHとLHの分泌を抑制することで排卵を抑制する。
2.(×)コンドームの避妊効果は約85%である。
3.(×)基礎体温法は月経不順があると不確実である。
4.(×)子宮内避妊具〈IUD〉は1度子宮内に挿入すれば5年間有効である。
第111回(2022年)
第6問:正常新生児の卵円孔の機能的閉鎖に関する説明で正しいのはどれか。
- 動脈血酸素分圧(PaO2)の上昇によって閉鎖する。
- ハイ血流の増加によって起こる。
- 出生から数週間後に閉鎖する。
- 動脈管の閉鎖が要因となる。
解答・解説
1.(×)動脈血酸素分圧の上昇は肺血管抵抗を減少させ、肺血流を増加させる。これにより、動脈管を通る血液が減るため、動脈管が閉鎖する。
2.(〇)第一啼泣時に吸入された空気によって肺が拡張すると、肺血流が増加し左心房圧が上昇する。この圧力によって卵円孔を覆う弁が心房中隔に押し付けられ、卵円孔が閉鎖する。
3.(×)卵円孔は、出生後数週間から数か月以内に自然に閉鎖する。
4.(×)卵円孔の機能的閉鎖は、左心房圧の上昇が要因となる。
第113回(2024年)
第7問:子宮復古状態を観察する手順で正しいのはどれか。
- 観察は排尿前に行う。
- 褥婦にはFowler(ファウラー)位をとってもらう。
- 褥婦の膝を伸展させて子宮底の高さを測定する。
- 子宮底長は恥骨結合下縁から測定する。
解答・解説
1.(×)膀胱内に尿が充満することで子宮底が上がるため、排尿後に観察する。
2.(×)子宮復古の観察時には、褥婦に仰臥位になってもらう。
3.(〇)子宮底の高さを測定するときには、褥婦の膝を伸展させた状態で行う。
4.(×)子宮底長は恥骨結合上縁から測定する。
第109回(2020年)
第8問:受精と着床についての説明で正しいのはどれか。
- 卵子が受精能をもつ期間は排卵後48時間である。
- 卵管采で受精が起こる。
- 受精卵は受精後4、5日で子宮に到達する。
- 受精卵は桑実胚の段階で着床する。
解答・解説
1.(×)卵子が受精能をもつ期間は排卵後24時間である。
2.(×)卵管膨大部で受精が起こる。
3.(〇)受精卵は卵管を通り、受精後4、5日で子宮に到達する。
4.(×)受精卵は胚盤胞の段階で着床する。
第110回(2021年)
第9問:早産期の定義はどれか。
- 妊娠21週0日から36週6日
- 妊娠22週0日から36週6日
- 妊娠22週0日から37週6日
- 妊娠23週0日から37週6日
解答・解説
1.(×)早産期とは妊娠22週0日から36週6日であり、妊娠37週0日~41週6日までの出産が正期産である。
2.(〇)
3.(×)
4.(×)
第110回(2021年)
第10問:新生児の呼吸の生理的特徴で適切なのはどれか。
- 成人に比べて肺のガス交換面積が大きい。
- 周期性呼吸がみられる。
- 胸式呼吸が主である。
- 口呼吸が主である。
解答・解説
1.(×)成人に比べて新生児は肺のサイズが小さく、ガス交換面積も小さい。
2.(〇)新生児期には、10~15秒の規則的な呼吸のあと短時間呼吸を止める「周期性呼吸」がみられる。
3.(×)新生児期から5歳ごろまでは腹式呼吸が主である。
4.(×)新生児期は鼻呼吸が主である。
第111回(2022年)
第11問:閉経について正しいのはどれか。
- 閉経すると腟の自浄作用が低下する。
- 閉経後はエストロゲン分泌が増加する。
- 日本人の閉経の平均年齢は55歳である。
- 10か月の連続した無月経の確認で診断される。
解答・解説
1.(〇)閉経後はエストロゲンの分泌が低下するため、膣の自浄作用は低下する。
2.(×)閉経後はエストロゲンの分泌が低下する。
3.(×)日本人の閉経の平均年齢は約50歳である。
4.(×)閉経とは卵巣の活動性が低下・消失し、月経が永久に停止した状態であり、12か月以上の連続した無月経の確認で診断される。
第112回(2023年)
第12問:順調に分娩が進行している産婦から「腟から水っぽいものが流れ、下着が濡れた」と看護師に訴えがあった。流出したものを確認すると、量は少量で、羊水特有の臭いを認めた。その時の産婦への対応で優先されるのはどれか。
- 更衣を促す。
- 体温を測定する。
- 食事摂取を勧める。
- 胎児心拍数を確認する。
解答・解説
1.(×)前期破水の可能性が高いため、清潔なパッドと下着に交換することは必要であるが、優先度は低い。
2.(×)前期破水では感染のリスクが高まるが、破水直後での体温測定の優先度は低い。
3.(×)前期破水後にまず食事摂取を勧める必要性は低い。
4.(〇)前期破水の合併症として、臍帯脱出や常位胎盤早期剝離などあるため、胎児心拍数の確認が優先される。
第109回(2020年)
第13問:産褥期の生理的変化で正しいのはどれか。
- 児が乳頭を吸啜することによってオキシトシンが分泌される。
- 子宮が非妊時の大きさに戻るのは分娩後約2週である。
- 分娩後は一時的に尿量が減少する。
- プロゲステロンが増加する。
解答・解説
1.(〇)児の吸啜刺激が視床下部に伝わるとオキシトシンが分泌される。
2.(×)子宮が非妊時の大きさに戻るのは分娩後約6~8週である。
3.(×)産褥早期には心房性ナトリウム利尿ペプチド(ANP)の増加がみられることもあり、一時的に尿量が増加する。分娩後に一時的な尿閉がみられることもある。
4.(×)分娩後、エストロゲンとプロゲステロンは急激に減少する。
第112回(2023年)