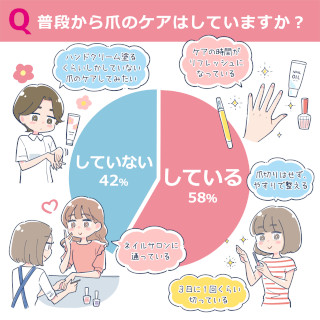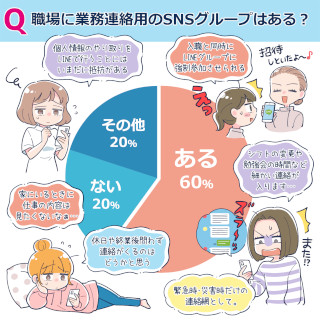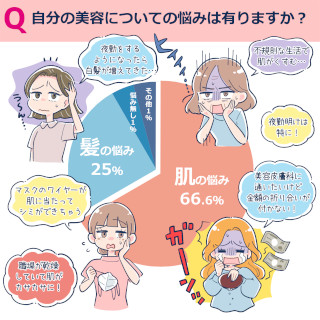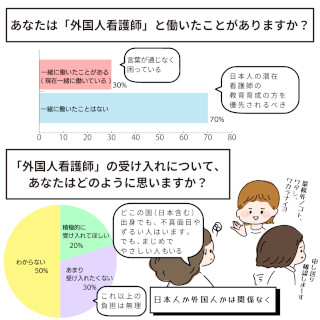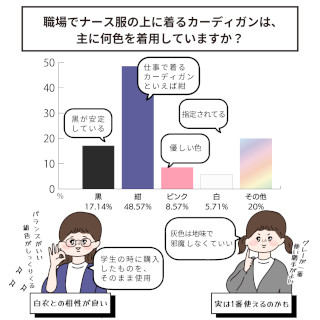2024年11月4日からスタートした1日3問国試ドリルは、月~金で1日3問ずつ配信しています。
このページでは、1日3問国試ドリルで配信した問題のうち、「小児看護学」に該当する問題と解答・解説を掲載します。振り返りにぜひ活用してください。【※毎週更新予定】
第1問:新生児の出血性疾患で正しいのはどれか。
- 生後48時間以内には発症しない。
- 母乳栄養児は発症のリスクが高い。
- 予防としてカルシウムを内服する。
- 早期に現われる所見に蕁麻疹がある。
解答・解説
1.(×)新生児におけるビタミンK欠乏性出血症は、生後2~4日目におこることが多く、生後24時間以内の発症もある。
2.(〇)母乳中にビタミンK含有量が少ないため、母乳栄養児は発症リスクが高い。
3.(×)予防にはビタミンK製剤の内服が有効である。
4.(×)症状として吐血や下血がみられる。
第111回(2022年)
第2問:幼児の心肺蘇生における胸骨圧迫の方法で正しいのはどれか。
- 胸骨中央下部を圧迫する。
- 実施者の示指と中指とで行う。
- 1分間に60回を目安に行う。
- 1回の人工呼吸につき3回行う。
解答・解説
1. (〇)幼児に対する胸骨圧迫は、胸骨中央下部を圧迫する。
2.(×) 実施者の示指と中指(あるいは中指と環指)とで行う胸骨圧迫は、乳児に対して行う方法である。幼児に対しては手掌で行う。
3.(×)幼児に対する胸骨圧迫は、100~120回/分を目安に行う。
4.(×)幼児に対する胸骨圧迫と人工呼吸の比率は、30:2である。
第109回(2020年)
第3問:新生児マススクリーニング検査(先天性代謝異常等検査)で正しいのはどれか。
- 対象疾患数は5つである。
- 唾液を用いた検査である。
- 早期新生児期に実施される。
- 治療法が確立していないし疾患を対象とする。
解答・解説
1.(×)新生児マススクリーニング検査は、先天性代謝異常などの疾患を見つける検査で、対象疾患数は23疾患である(2024年10月現在)
2.(×)踵から少量の血液を採取して検査する。
3.(〇)生後4週間までを新生児といい、生後1週間以内の新生児は早期新生児という。新生児マススクリーニング検査は日齢4~6日目(出生日を0日とする)に行うため、早期新生児期に実施される。
4.(×)新生児マススクリーニング検査は、正常児の中から、治療可能で、かつ放置すれば心身障害を引き起こす疾患を持つ子どもの早期発見・治療を行い、障害の発生を予防する目的で実施される。
第113回(2024年)
第4問:正常な幼児期の基本的生活習慣で、2歳0か月ころまでに習得するのはどれか。
- 鼻をかむ。
- スプーンを使う。
- 夜間のおむつがとれる。
- 洋服のボタンをとめる。
解答・解説
1.(×)おおむね4歳で鼻をかむことができるようになる。
2.(〇)おおむね1歳6か月でスプーンを使うことができるようになる。
3.(×)おおむね3~4歳で夜間のおむつがとれるようになる。
4.(×)おおむね3歳6か月でボタンをとめられる。
第112回(2023年)
第5問:健康な小児の成長・発達で正しいのはどれか。
- 情緒は快から不快が分化する。
- 発達とともにレム睡眠の割合は増える。
- 体重は出生後1年で出生時の約4倍になる。
- 身長は出生後1年で出生時の約1.5倍になる。
解答・解説
1.(×)興奮から快・不快に分化する。
2.(×)発達とともにレム睡眠の割合は減少する。
3.(×)体重は出生後1年で出生時の約3倍になる。
4.(〇)身長は出生後1年で出生時の約1.5倍になる。
第110回(2021年)
第6問: 乳幼児身体発育調査による、身体発育曲線のパーセンタイル値で正しいのはどれか。
- 3パーセンタイル未満の児は、要精密検査となる。
- 50パーセンタイルは同年齢同性の児の平均値を示す。
- 10パーセンタイルは同年齢同性の児の平均より10%小さいことを示す。
- 75パーセンタイル以上90パーセンタイル未満の児は、要経過観察となる。
解答・解説
1.(〇)3パーセンタイル未満と97パーセンタイル以上の児は、要精密検査となる。
2.(×)50パーセンタイルは同年齢同性の児の中央値を示す。
3.(×)10パーセンタイルは同年齢同性の児のうち、小さいほうから数えて10%目の数値に当たる。
4.(×)3パーセンタイル前後で発育曲線に沿って増加がみられている場合には経過観察となる。
第110回(2021年)
第7問: Aちゃん(11歳、女児)は、5日前から両側の眼瞼浮腫と急な体重増加があり、尿量が少ないため来院した。高度の蛋白尿もみられたため入院し、ネフローゼ症候群と診断されステロイド治療の方針となった。現時点でのAちゃんへの看護で適切なのはどれか。
- 水分摂取を促す。
- 病院内を散歩して良いと伝える。
- 糖分の摂取制限があることを伝える。
- 一時的に満月様顔貌になることを説明する。
解答・解説
1.(×)ネフローゼ症候群で浮腫が認められているため、水分摂取を促すことはせず指示量を守ってもらう。
2.(×)浮腫のある時期には安静を保つことにより尿量が増加し、浮腫も軽減するため、散歩は不適切である。
3.(×)糖分の摂取制限は必要ない。
4.(〇)
ステロイド治療により満月様顔貌になることがある。服薬中の症状であるため、一時的である。
第110回(2021年)
第8問:生後11か月の男児。ある日の朝、自宅でボタン型電池を飲み込んだ疑いがあり、その日の午前中に外来を受診した。胸部エックス線撮影によって、ボタン型電池が食道下部にあることが確認された。行われる処置で適切なのはどれか。
- 背部の叩打
- 緩下薬の使用
- 催吐薬の使用
- 緊急摘出術の実施
解答・解説
1.(×)背部の叩打は成人に対する気道異物除去法である。
2.(×)緩下薬は、薬物や有毒物質などによる急性中毒に対する消化管除染などで使用される。
3.(×)催吐薬はタバコや薬物などの誤飲時に胃内容物を吐き出させる目的で使用される。
4.(〇)ボタン型電池を誤飲した場合、短時間で消化管壁が損傷し、潰瘍や穿孔がおこるため、早急な摘出が必要である。
第111回(2022年)
第9問: 乳児に対する一次救命処置(BLS)で正しいのはどれか。
- 脈拍の確認は橈骨動脈の触知で行う。
- 意識レベルは足底を叩きながら反応を確認する。
- 救助者が2名いる場合、胸骨圧迫と人工呼吸の回数の比率は30:2である。
- 胸骨圧迫の速さ(回数)は130~150回/分である。
解答・解説
1.(×)乳児に対するBLSにおいて、脈拍の確認は上腕動脈の触知で行う。1~15歳の小児では頸動脈、大腿動脈の触知を行う。
2.(〇)意識レベルの確認は、足底を軽くたたいて行う。
3.(×)救助者が2名いる場合には、胸骨圧迫と人工呼吸の回数比率は15:2で行う。救助者が1名の場合は、30:2である。
4.(×)胸骨圧迫の速さ(回数)は成人と同様で100~120回/分である。
第113回(2024年)
第10問: 出生体重3020gの正期産児。新生児期に最もチアノーゼを生じやすい先天性心疾患はどれか。
- 動脈管開存症
- 心室中隔欠損症
- 心房中隔
- Fallot(ファロー)四徴症
解答・解説
1.(×)動脈管開存症は、動脈管(大動脈と肺動脈をつなぐ血管)が、出生後も自然閉鎖せずに開存した状態が続く疾患であり、非チアノーゼ性心疾患である。
2.(×)心室中隔欠損症は心室中隔に孔があいている先天性心疾患であり、非チアノーゼ性心疾患である。
3.(×)心房中隔欠損症は心房中隔に孔があいている先天性心疾患であり、非チアノーゼ性心疾患である。
4.(〇)ファロー四徴症は、先天性のチアノーゼ性心疾患で最も頻度が高い疾患である。 心臓の先天的な異常によって、酸素化されない静脈血が動脈血に流入することでチアノーゼが生じる。
第113回(2024年)
第11問:下腿の開放骨折のため手術を受けたA君(8歳、男児)に、術後の疼痛管理のため患者自己調節鎮痛法(Patient Controlled Analgesia:PCA)を用いた持続的な静脈内注射を行うことになった。A君は「痛くなるのが怖い」と話している。看護師はA君に鎮痛薬の追加について説明することにした。A君への説明で適切なのはどれか。
- 「時間を決めて操作ボタンを押そうね」
- 「痛くなり始めたら操作ボタンを押そうね」
- 「痛くなったら何回でも操作ボタンを押してお薬を追加できるよ」
- 「痛みがどうしても我慢できなくなったら操作ボタンを押そうね」
解答・解説
1.(×)患者自己調節鎮痛法は、患者が痛みのあるときに患者自身にPCAポンプを操作してもらい、安全かつ効果的な量の鎮痛剤を投与する方法である。痛みのないときに押す必要はなく、時 間を決めて操作ボタンを押す必要はない。
2.(〇)ボタンを押してすぐに痛みがなくなるわけではないため、痛くなり始めたら操作ボタンを押すよう伝えるのは適切である。
3.(×)ロックアウト時間を設定することで過剰投与は起こらないが、薬が毎回追加されると誤認させるため、不適切である。
4.(×)痛みを我慢させる必要はないため、不適切である。
第113回(2024年)
第12問:乳歯について正しいのはどれか。
- 永久歯より石灰化度が高い。
- 生後8か月に生えそろう。
- 胎児期に石灰化が始まる。
- 本数は永久歯と同じである。
解答・解説
1.(×)乳歯はエナメル質の石灰化度が低く、齲歯(むし歯)になりやすい。
2.(×)乳歯が生えそろうのは2歳半~3歳半頃である。
3.(〇)乳歯は胎児期に石灰化が始まる。
4.(×)乳歯は20本あるのに対し、永久歯は第三大臼歯(親知らず)を除くと28本ある。
第112回(2023年)
第13問:新生児や乳児が胎児期に母体から受け取った抗体は次のどれか。
- IgA
- IgD
- IgG
- IgM
解答・解説
1.(×)IgAは人の腸管、気道などの粘膜や初乳に存在する抗体である。
2.(×)IgDはB細胞の表面に存在する抗体である。
3.(〇)IgGは抗体の中で唯一胎盤を通過できる。
4.(×)IgMはB細胞から産生される抗体である。
第111回(2022年)