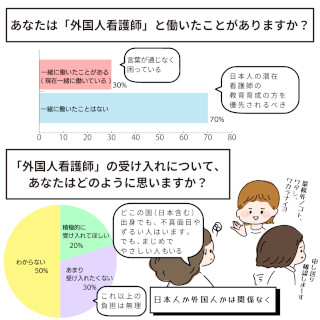医療の場が在宅へと比重が高まるものの、まだまだ知られていない訪問看護。ここでは訪問看護の実際について、エピソードを通じてご紹介します。
うちの社長はともかく前を見ている。
前しか見ていないと言っても過言ではないかもしれない。
社長がうちの訪問看護ステーションを立ち上げたのは8年前。始めは社長を含め、3人だけの看護師だったのが、現在11名の看護スタッフを抱えるまでの大きい訪問看護ステーションになった。
ここまで訪問看護ステーションを大きくするまでには、いろんな苦労もされてきたが、どんな状況下でも、「ここが踏ん張り時です」と常に下を向かず顔をあげてこられた社長。50代から多忙の中、言語聴覚士の資格をとるために学生になったことも・・・。
「振り返るとあっと言う間でしたね・・・」と眼を細められた。
訪問看護ステーションの社長が看護師を目指したきっかけ
社長が6歳の頃、祖父を看取ったのが、看護師を目指すきっかけになったとか・・・。
当時、裕福ではなかった暮らしの中で、家族で分担をして祖父の介護をされていたとのこと。 母は早朝と夜に清拭とオムツ交換、日中は働きに出かけ、9歳の兄は新聞配達と祖父の食事介助、社長は当時6歳で尿瓶を破棄する係りだったそうだ。
家族で働いたお金をみんなで持ち寄り、これだけのお金でやりくりしようねと生活していたため、家族は結束を増し、特に辛いという感情はなかったと。
「月に一度の外食はタヌキうどんでね。質素なものだったけどとても嬉しくて・・・。その後に食べる小豆アイスの味は忘れられないですね」と。
そんなある日、当時6歳の社長が祖父の尿瓶を捨てにいこうと部屋を訪れたら、祖父が既に冷たくなっていたそうである。
「頭が真っ白になりましたね。人って死ぬとこんなに冷たくなるんだと、漠然と感じていました」
しかし、当時6歳の社長は、死というものがどういうものかわからなかったという。
当時のお葬式は湿っぽいものでなく、お餅をまいたりして賑やかに過ぎていき、往診に来られていた先生と看護師さんも参列され、手を合わされたとか。
その姿をみた時に初めて、『ああ、本当に死んでしまったんだな』と実感されたそうである。
毎回往診にこられる先生と看護師をいつも側で見ていたこともあり、家で人が自然な形で亡くなっていくことや、家族で団結して介護をしていくということが、当たり前のように頭の中に流れこんできた小学生時代。
いつしか、自分も『自宅でその人らしい人生を終わらせるお手伝いをしたい』という想いが芽生え、中学生になる時には、将来看護師になりたいと決意されていたそうだ。
社長が医療に携わるモチベーションは
「人は1人では生まれてこれないし、1人では死ねないんです。だから、始めと最後は人の手をかりて初めて成り立つものなんですよ」と。
そしてまた、 「医療者の仕事は24時間365日です。病気に休みはありませんからね」とも。
その言葉の通り、社長は現在も365日殆ど休むことなく現場にも顔を出しながら仕事をされている。あまりに休まないため、部下が心配するほど。
しかし、社長は心配する部下にこんな風に返す。
「こんなやりがいのあるお仕事、もったいなくて休んでなんていられません。看護をさせていただける有難さ!感謝感謝です!」
まさに天職というところだろうか。
「人はみんな死ぬんです」
だからこそ、利用者様に残された時間を、少しでも輝かせるお手伝いが出来ることを願い、今日も私達は訪問に出かけてゆく。