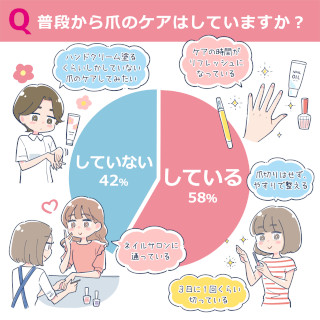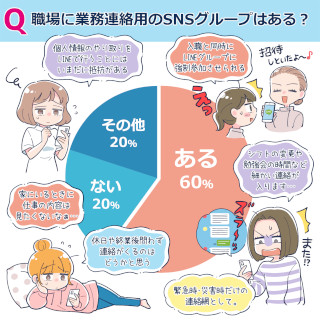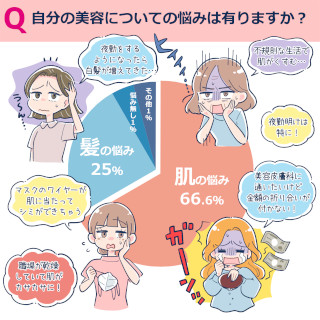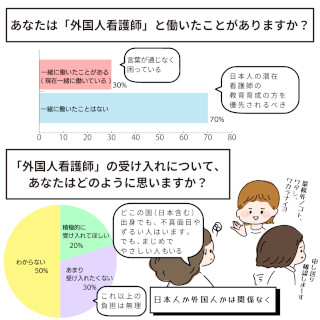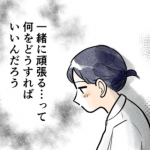2024年11月4日からスタートした1日3問国試ドリルは、月~金で1日3問ずつ配信しています。
このページでは、1日3問国試ドリルで配信した問題のうち、「精神看護学」に該当する問題と解答・解説を掲載します。振り返りにぜひ活用してください。【※毎週更新予定】
第1問:アルコールを多飲する人によくみられ、意識障害、眼球運動障害および歩行障害を特徴とするのはどれか。
- 肝性脳症
- ペラグラ
- ウェルニッケ脳症
- クロイツフェルト・ヤコブ病
解答・解説
1.(×) 肝性脳症は急性・慢性肝不全にみられる精神・神経症状で、異常行動や傾眠、羽ばたき振戦などの症状がみられる。
2.(×) ペラグラはナイアシン欠乏症で、皮膚炎、胃腸炎、認知機能低下などの症状がみられる。
3.(〇)ウェルニッケ脳症はビタミンB1欠乏でみられ、眼球運動障害や意識障害、歩行障害などを特徴とする。ウェルニッケ脳症の原因の半分はアルコール依存症が占める。
4.(×) クロイツフェルト・ヤコブ病は、脳に異常なプリオン蛋白が沈着し、認知症が急速に進行する疾患。行動異常、性格変化や認知症、視覚異常、歩行障害などの症状がみられる。
第110回(2021年)
第2問:Aさん(22歳、統合失調症)は父親、母親、妹との4人暮らし。高校卒業後、アルバイトをしていたが、症状の悪化によって初めて精神科病院に入院した。退院後に一般企業で働きたいと希望している。看護師がAさんに提案するサービスで適切なのはどれか。
- 行動援護
- 就労移行支援
- 自立生活支援
- 地域定着支援
解答・解説
1.(×) 行動援護は知的障害や精神障害により、自分一人で行動することが著しく困難であり、常時介護を要する障害者が対象である。
2.(〇)Aさんは一般企業での就労を希望しており、就労移行支援を提案するのは適切である。
3.(×) 自立生活援助は、居宅において単身で生活する障害者(家族と同居しているが支援が見込めない場合も含む)に対して定期的な巡回訪問や随時の対応によって自立した生活を支援するものである。
4.(×) 地域定着支援は、居宅において単身で生活する障害者(家族と同居しているが支援が見込めない場合も含む)に対して常時の連絡体制の確保や緊急時の対応などの支援を行うものである。
第111回(2022年)
第3問:飲酒したい欲求を抑圧した人が、酩酊状態の人の行動を必要以上に非難する防衛機制はどれか。
- 昇華
- 転換
- 合理化
- 反動形成
解答・解説
1.(×) 欲求を社会的に歓迎される形に変換することを昇華という。
2.(×)転換は置き換えともいい、現実的に叶えることが難しい願望をほかのことで補うことをいう。
3.(×)自分にとって心地悪い葛藤を高めないための行動や考え方、態度や感情のことを合理化という。
4. (〇)自分の欲求を抑えるため、欲求と正反対の行動をとることを反動形成という。飲酒したい欲求を、飲酒ができる人への非難に逆転させている。
第109回(2020年)
第4問:Aさん(30歳、男性)は、昼間の過剰な眠気を主訴に来院した。会社の会議ではいつも寝てしまい、居眠り運転で交通事故を起こしたこともある。笑ったときに脱力してしまうことや、入眠時に誰もいないのに人影が見えたり、睡眠と覚醒の移行期に体を動かせなくなることがある。最も考えられる疾患はどれか。
- ナルコレプシー
- レム睡眠行動障害
- 睡眠時無呼吸症候群
- レストレスレッグス症候群(むずむず脚症候群)
解答・解説
1.(〇)ナルコレプシーは、耐えがたい眠気の出現や、歩行中や食事中、運転中などに突然居眠りしてしまう慢性の睡眠障害である。喜怒哀楽の強い感情によって、筋緊張が一時的に消失する情動脱力発作(カタプレキシー)、レム睡眠への移行時に関連した幻覚、睡眠麻痺が特徴である。 Aさんの症状はナルコレプシーの可能性が高いといえる。
2.(×)レム睡眠行動障害は、睡眠中に突然大声や奇声を上げたり、暴力的な行動をとったりする。本来、レム睡眠中は骨格筋が弛緩するが、レム睡眠行動障害では神経調節システムの障害によって夢の中の行動がそのまま表れる。
3.(×)睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に呼吸停止が頻回に起こり、酸素の取り込みが妨げられて酸素飽和度が低下する。十分な睡眠がとれなくなるため、日中の居眠りや注意力散漫につながる。
4.(×)レストレスレッグス症候群は、下肢を中心とした異常感覚によって不眠、過眠を引き起こす。夕方から深夜にかけて出現するのが特徴である。
第113回(2024年)
第5問:小児期から青年期に発症し、運動性チック、音声チック及び汚言の乱用を伴うのはどれか。
- Down〈ダウン〉症候群(Down’ssyndromeown)
- Tourette〈トゥレット〉障害(Tourette’sdisorder)
- 注意欠如・多動性障害〈ADHD〉(attention-deficit/hyperactivit)
- Lennox-Gastaut〈レノックス・ガストー〉(Lennox-Gastaut)症候群(syndrome)
解答・解説
1.(×) ダウン症候群は21番染色体が3本あることで起こる先天異常症候群である。主な症状としては、筋緊張低下、短い鼻・小さい耳・丸く平坦な顔貌などがみられる。
2.(〇)トゥレット症候群は、運動性チックや音声チックが1年以上持続する精神神経疾患である。汚言の乱用は音声チックの一種である。
3.(×) 注意欠如・多動性障害は発達障害のひとつで、注意の持続や順序立てた行動が困難である、落ち着きがないなどの症状によって日常生活に困難が起こっている状態である。
4.(×) レノックス・ガストー症候群はてんかん症候群のひとつで、強直発作や非定型欠神発作などのてんかん発作や知的障がいがみられる。
第112回(2023年)
第6問:母親がAさん(27歳、統合失調症)に対して「親に甘えてはいけない」と言いながら、過度にAさんの世話をすることで、Aさんが混乱していた。 この親子関係を示すのはどれか。
- 共依存
- 同一視
- ネグレクト
- 二重拘束〈ダブルバインド〉
解答・解説
1.(×)共依存とは特定の相手に必要とされることに存在価値を見いだし、互いに依存する状態である。
2.(×)同一視とは特定の相手のようになりたいと思い、同じようにふるまったり、対象の考え方を自己の内面に取り込んだりする状態である。
3.(×)ネグレクトとは幼児・高齢者などの社会的弱者に対し、その保護や養育義務を果たさず放任する行為のことである。
4.(〇)二重拘束〈ダブルバインド〉とは、相反する言語的なメッセージや非言語的なメッセージを一度に受け、どちらに従って行動したらいかわからなくなる状態である。母親の言動と行動は相反しておりAさんの混乱を招いているため、この親子関係は二重拘束〈ダブルバインド〉である。
第111回(2022年)
第7問:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉に基づき、精神障害者に適用されるのはどれか。
- 障害基礎年金
- 一定割合の雇用義務
- 精神障害者保健福祉手帳
- 自立支援医療(精神通院医療)
解答・解説
1.(×)障害基礎年金は、国民年金の障害等級表で定められた1級・2級にあたる障害がある人に適用される。国民年金法に規定されている。
2.(×)障害者雇用促進法により、従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を法定雇用率以上にする義務がある。
3.(×)精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するもので、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に規定されている。
4.(〇)自立支援医療(精神通院医療)とは、障害者等につきその心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活を営むために必要な医療のことで、障害者総合支援法に基づき、精神障害者に適用される。
第112回(2023年)
第8問:都道府県知事に対し、精神科病院に医療保護入院となっている患者の退院請求をすることができるのはどれか。
- 警察官
- 検察官
- 患者本人
- 精神保健福祉士
解答・解説
1.(×)警察官は退院請求できない。
2.(×)検察官は退院請求できない。
3.(〇)都道府県知事に対して、精神科病院に医療保護入院となった患者の退院請求ができるのは、患者本人または家族等である。家族等とは、配偶者、親権者、扶養義務者、後見人または保佐人をいう。
4.(×)精神保健福祉士は退院請求できない。
第113回(2024年)
第9問:選択的セロトニン再取り込み阻害薬〈SSRI〉で正しいのはどれか。
- パニック障害に対して有効である。
- 抗コリン作用は三環系抗うつ薬よりも強い。
- うつ症状が改善したら使用はすぐ中止する。
- 抗うつ効果の評価は使用開始後3日以内に行う。
解答・解説
1.(〇)選択的セロトニン再取り込み阻害薬〈SSRI〉はパニック障害やうつ病の治療に用いられる。
2.(×)抗コリン作用は三環系抗うつ薬のほうが強い。
3.(×)選択的セロトニン再取り込み阻害薬〈SSRI〉は、急に中止すると断薬症状としてパニック発作と似た症状(めまい、発汗、吐き気など)が出ることがある。
4.(×)抗うつ効果の評価は使用開始後4週間目に行う。
第110回(2021年)
第10問:大規模災害が発生し、被災した住民は自治体が設置した避難所に集まり避難生活を始めた。発災3日、自治体から派遣された看護師は避難所の片隅で涙ぐんでいるAさんへの関わりを始めた。Aさんは「悲しい気持ちが止まりません」と話している。 このときのAさんへの看護師の発言で適切なのはどれか。
- 「災害以外のことを何か考えましょう」
- 「あなたの悲しい気持ちは乗り越えられるものですよ」
- 「悲しい気持ちが止まらないのは異常なことではないですよ」
- 「みんなが大変なのですからAさんも元気を出してください」
解答・解説
1.(×)被災者のストレス反応の軽減方法として、被災体験を聴くことが最もよいとされている。
2.(×)安易な励ましは不適切である。
3.(〇)Aさんの気持ちを聴き、その感情を受容する発言が適切である。
4.(×)Aさんの悲しいという気持ちを否定するような発言は不適切である。
第112回(2023年)
第11問:攻撃性の高まった成人患者への対応で正しいのはどれか。
- 患者の正面に立つ。
- アイコンタクトは避ける。
- 身振り手振りは少なくする。
- ボディタッチを積極的に用いる。
解答・解説
1.(×)対象の真正面に立つのを避け、斜め 45°の立ち位置とする。
2.(×)凝視を避けるが、完全に目をそらさずアイコンタクトは保つ。
3.(〇)身体の動きは最小限にし、身振り手振りが多過ぎることや、そわそわと身体を揺すったり、身体の重心を移動させたりするのを避ける。
4.(×)警告なしに相手に触れたり、接近したりしない。
第110回(2021年)
第12問:一般の事業所や企業に就労を希望する精神障害者に対して行う支援で、24か月間を原則として就職に必要な訓練や求職活動を行うのはどれか。
- 就労移行支援
- 自立生活援助
- ピアサポート
- 就労継続支援A型
解答・解説
1.(〇)就労移行支援とは、一般就労等への移行に向けて、事業所内や企業における作業や実習、適性に合った職場探し、就労後の職場定着のための支援などを行うものであり、利用期間は24か月間である。
2.(×)自立生活援助は、居宅にて単身等で生活する障害者に対し、訪問や相談対応によって問題の把握を行い、必要な情報の提供・助言、相談、関係機関との連絡調整等の自立した日常生活を営むために必要な援助を行うもので、標準利用期間は1年間である。
3.(×)ピアサポートは、自ら障害や疾病の経験を持ち、その経験を生かしながら、他の障害や疾病のある障害者のための支援を行うものである。
4.(×)就労継続支援A型は、一般企業に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して、雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供を行うものである。
第112回(2023年)
第13問:Aさん(43歳、男性)は統合失調症で通院していたが、服薬中断によって幻覚妄想状態が続いていた。ある日、Aさんの父親に対する被害妄想が強くなり、父親へ殴りかかろうとしたところを母親に制止された。その後、Aさんは母親に促されて精神科病院を受診し「薬は飲みたくないけど、父親が嫌がらせをするので、すぐに入院して家から離れたい」と訴えた。母親も入院治療を強く希望している。Aさんの入院形態はどれか。
- 応急入院
- 措置入院
- 任意入院
- 医療保護入院
解答・解説
1.(×)応急入院は、入院を必要とする精神障害者で、任意入院を行う状態になく、急を要し、保護者の同意が得られない者が対象となる。
2.(×)措置入院は、入院させなければ自傷他害のおそれのある精神障害者が対象となる。
3.(〇)任意入院は、入院を必要とする精神障害者で、入院について本人の同意がある者が対象となる。Aさんは入院に対して同意しているため、任意入院となる。
4.(×)医療保護入院は、入院を必要とする精神障害者で、自傷他害のおそれはないが、任意入院を行う状態にない者が対象となる。
第113回(2024年)