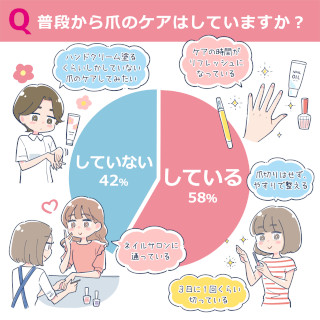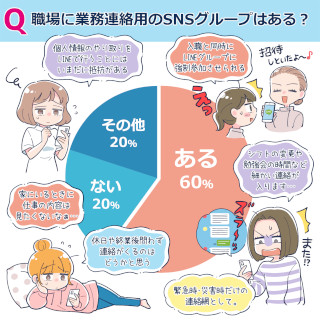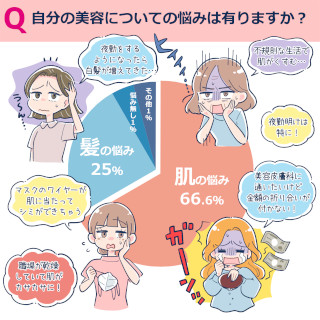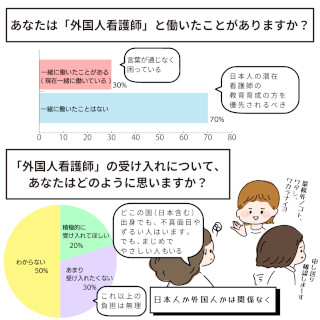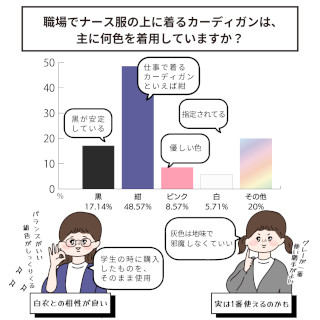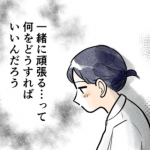2024年11月4日からスタートした1日3問国試ドリルは、月~金で1日3問ずつ配信しています。
このページでは、1日3問国試ドリルで配信した問題のうち、「基礎看護学」に該当する問題と解答・解説を掲載します。振り返りにぜひ活用してください。【※毎週更新予定】
第1問:医療器材と消毒・滅菌の組み合わせで正しいのはどれか。
- 手術用持針器 — 第4級アンモニウム塩
- ステンレス製便器 — 熱水消毒
- 軟性内視鏡 — 高圧蒸気滅菌
- ベッド柵 — グルタラール
解答・解説
1.(×) 手術用持針器はクリティカル器具(人体の無菌の組織や血管系に使用する器具)のため、洗浄+滅菌(高圧蒸気滅菌やガス滅菌など)が適切である。
2.(〇) ステンレス製便器はノンクリティカル器具(健常な皮膚にのみ接触する器具)のため、洗浄+熱水消毒が適切である。
3.(×) 軟性内視鏡はセミクリティカル器具であり、洗浄+高水準消毒(グルタラール、フタラールなど)が適切である。
4.(×) ベッド柵などの環境表面の消毒は、低水準消毒薬(ベンザルコニウム塩化物、アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩など)やアルコール、次亜塩素酸ナトリウムなどが用いられる。
第111回(2022年)
第2問:輸血用血液製剤と保存温度の組合せで正しいのはどれか。
- 血小板成分製剤 — 2〜6℃
- 赤血球成分製剤 — 2〜6℃
- 血漿成分製剤 — 20〜24℃
- 全血製剤 — 20〜24℃
解答・解説
1.(×)血小板成分製剤の保存温度は20~24℃で、穏やかに振とうする必要がある。
2.(〇) 赤血球の保存温度は2~6℃である。
3.(×)血漿成分製剤の保存温度は-20℃以下である。
4.(×)全血製剤の保存温度は2~6℃である。
第112回(2023年)
第3問:成人女性に膀胱留置カテーテルを挿入する方法で適切なのはどれか。
- 水溶性の滅菌潤滑剤を用いる。
- カテーテルは外尿道口から15cm挿入する。
- 固定用バルーンを膨らませた後、尿の流出を確認する。
- 固定用バルーンにはクロルヘキシジングルコン酸塩液を注入する。
解答・解説
1.(〇)油性の潤滑剤はカテーテルを破損するため、水溶性の滅菌潤滑剤を用いる。
2.(×) 成人女性では外尿道口から4~5cm挿入する。
3.(×) カテーテルを挿入し尿の流出を確認したあと、固定用バルーンを膨らませる。
4.(×) 固定用バルーンには滅菌蒸留水を注入する。
第109回(2020年)
第4問:成人の前腕に静脈留置針を穿刺するときの刺入角度で適切なのはどれか。
- 10~20度
- 30~40度
- 50~60度
- 70~80度
解答・解説
1.(〇)成人の前腕に静脈留置針を穿刺するときの刺入角度は、10~20度が適切である。
2.(×)
3.(×)
4.(×)
第110回(2021年)
第5問:排痰を促す目的で行うのはどれか。
- タッチング
- スクイージング
- 漸進的筋弛緩法
- 持続的気道陽圧(CPAP)療法
解答・解説
1.(×)タッチングは非言語的コミュニケーションの一つで、患者の身体に触れることをいう。タッチングには患者に安心感を与えたり、不安をやわらげたりする効果がある。
2.(〇) スクイージングは排痰を促す手技である。痰が溜まっている胸郭の部位に手掌を当てて圧迫し、貯留した痰を気道へと移動させる。
3.(×) 漸進的筋弛緩法は、筋肉の緊張と弛緩を意図的に繰り返すことで身体のリラックスを促す方法である。不安や緊張の緩和、不眠の改善、疲労回復の効果が期待できる。
4.(×)持続的気道陽圧療法とは、機械で一定の圧力をかけた空気を鼻から気道に送り込み、気道を広げて睡眠中の無呼吸を防止する治療法である。
第113回(2024年)
第6問:成人の上腕での触診法による血圧測定で適切なのはどれか。
- ゴム囊中央が上腕の正中線に沿うように合わせる。
- マンシェットの幅は13~17cmのものを使用する。
- 加圧後1秒ごとに10mmHg下がる速さで減圧する。
- 動脈の拍動が触知できなくなった値からさらに40mmHg加圧する。
解答・解説
1.(×)ゴム囊中央が上腕動脈の真上にくるように合わせる。
2.(〇)
適正なマンシェットの幅は、腋窩から肘窩までの長さの2/3である。成人の場合、13~17cmが適切である。
3.(×)3mmHg/秒くらいを目安に減圧する。
4.(×)動脈の拍動が触知できなくなった値からさらに20mmHg加圧する。
第110回(2021年)
第7問:Aさん(24歳、男性)は急性虫垂炎の術後1日で、ベッド上で仰臥位になり右前腕から点滴静脈内注射が行われている。Aさんは左利きである。病室外のトイレまでAさんが移動するための適切な療養環境はどれか。
- 履物はAさんの左手側に置く。
- ベッド柵はAさんの右手側に設置する。
- 輸液スタンドはAさんの左手側に置く。
- ベッドは端座位にAさんの足底が床につく高さにする。
解答・解説
1.(×)ルート誤抜去防止のため、テンションのかかりにくい右側からの離床が望ましい。履物は右側に置く。
2.(×)Aさんは右手に点滴静脈内注射をしており、右側からの離床が望ましいため、ベッド柵は左手側に設置する。
3.(×)ルート誤抜去防止のため、輸液スタンドは点滴静脈内注射が行われている右側に置く。
4.(〇)端坐位時に足底が床につく高さにベッドの高さを調整するのが正しい。
第111回(2022年)
第8問: 便の性状と原因の組合せで正しいのはどれか。
- 灰白色便──Crohn〈クローン〉病 Crohndisease
- 鮮紅色便──鉄剤の内服
- タール便──上部消化管出血
- 米のとぎ汁様便──急性膵炎 acutepancreatitis
解答・解説
1.(×)灰白色便は、乳幼児のロタウイルス感染性腸炎のほか、胆汁分泌低下や薬剤性肝障害などでみられる。
2.(×)鮮紅色便は下部消化管出血でみられる。上部消化管出血に比べ、未酸化のヘモグロビンが多くなり鮮紅色が強くなる。
3.(〇)タール便は上部消化管出血でみられる。赤血球中に含まれるヘモグロビン内の鉄分が酸化すると黒色となる。
4.(×)米のとぎ汁様便はコレラでみられる。
第112回(2023年)
第9問: 穿刺と穿刺部位の組合せで適切なのはどれか。
- 胸腔穿刺──胸骨柄
- 骨髄穿刺──第3・4腰椎間
- 腹腔穿刺──腹直筋外側の側腹部
- 腰椎穿刺──上前腸骨棘
解答・解説
1.(×)胸腔穿刺の穿刺部位は、気胸では第2肋間鎖骨中線上、胸水除去では第4~6肋間中腋窩線上が適切である。
2.(×)骨髄穿刺の穿刺部位は、腸骨(上後腸骨棘)が適切である。
3.(〇)腹腔穿刺の穿刺部位は腹直筋外側の側腹部が適切である。
4.(×)腰椎穿刺の穿刺部位は第3・4腰椎間もしくは第4・5腰椎間が適切である。
第112回(2023年)
第10問:呼吸音の変化と原因の組合せで正しいのはどれか。
- 呼気延長──胸水
- 呼吸音の減弱──過換気症候群
- 呼吸音の増強──無気肺
- 肺野での気管支呼吸音の聴取──肺炎
解答・解説
1.(×)呼気延長は、喘息やCOPDなどでみられる。
2.(×)呼吸音の減弱は、気胸、胸水、肺水腫、COPDなどでみられる。
3.(×)呼吸音の増強は、過換気症候群などでみられる。
4.(〇)肺野での気管支呼吸音の聴取は、肺炎や肺水腫などでみられる。
第110回(2021年)
第11問:臨死期の身体的変化はどれか。
- 尿量が増加する。
- 全身の筋肉が硬直する。
- 不規則な呼吸が出現する。
- 頸動脈が触れなくなった後、橈骨動脈が触れなくなる。
解答・解説
1.(×)臨死期は、経口摂取ができないこと、心機能・腎機能低下に伴う腎虚血状態になることから乏尿もしくは無尿となる。
2.(×)臨死期には全身の筋肉が弛緩する。
3.(〇)臨死期には、チェーン・ストークス呼吸や下顎呼吸など、不規則な呼吸がみられる。
4.(×)臨死期には、橈骨動脈が触れなくなる。
第112回(2023年)
第12問:仰臥位の患者の良肢位で正しいのはどれか。
- 肩関節外転90度
- 肘関節屈折90度
- 膝関節屈折90度
- 足関節屈折90度
解答・解説
1.(×)肩関節では、外転10~30度が良肢位である。
2.(〇)肘関節では、屈曲90度が良肢位である。
3.(×)膝関節では、屈曲10~20度が良肢位である。
4.(×)足関節では、背屈・底屈0度 が良肢位である。
第113回(2024年)
第13問: 成人に自動体外式除細動器〈AED〉を使用する際の電極パッドの貼付で正しいのはどれか。
- 小児用電極パッドが代用できる。
- 右前胸部に縦に並べて貼付する。
- 貼付部の発汗は貼付前に拭き取る。
- 経皮吸収型テープ剤の上に貼付する。
解答・解説
1.(×)小児用電極パッドは、成人に代用できない。成人用パッドを小児に代用することはできる。
2.(×)電極パッドは、右前胸部と左側胸部に1枚ずつ貼る。
3.(〇)傷病者の胸が汗や水で濡れている場合は、タオル等でふき取る。
4.(×)胸部に経皮吸収型テープ剤がある場合は、はがして胸をふいてから電極パッドを貼る。
第109回(2020年)