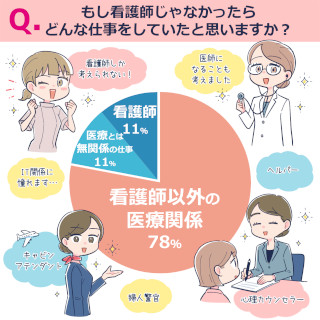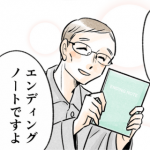2024年11月4日からスタートした1日3問国試ドリルは、月~金で1日3問ずつ配信しています。
このページでは、1日3問国試ドリルで配信した問題のうち、「人体の構造と機能」に該当する問題と解答・解説を掲載します。振り返りにぜひ活用してください。【※毎週更新予定】
第1問:交感神経の興奮によって起こる眼の反応はどれか。
- 散瞳
- 流涙
- 明順応
- 対光反射
解答・解説
1.(〇)交感神経の興奮によって瞳孔散大筋が収縮し、瞳孔は散大する。
2.(×)交感神経の興奮によって涙はわずかに分泌が増え、副交感神経の興奮によって流涙が起こ
る。
3.(×)明順応は、瞳孔括約筋が収縮して光の量を少なくすることをいう。瞳孔括約筋は副交感神経が支配している。
4.(×)対光反射は一方の目に光を当てると、両目が縮瞳する自律神経反射である。縮瞳は瞳孔括約筋の収縮によるものであり、副交感神経が支配している。
第113回(2024年)
第2問:体温のセットポイントが突然高く設定されたときに起こるのはどれか。
- 立毛
- 発汗
- 代謝抑制
- 皮膚血管拡張
解答・解説
1.(〇)感染症などにより発熱物質が生成されると、体温中枢に作用し、体温のセットポイントが上昇する。熱放散を防ぐために血管が収縮するほか、悪寒、立毛、代謝亢進などの反応がみられる。
2.(×)
3.(×)
4.(×)
第109回(2020年)
第3問:健常な女子(15歳)が野外のコンサートで興奮し、頻呼吸を起こして倒れた。このときの女子の体内の状態で正しいのはどれか。
- アルカローシスである。
- ヘマトクリットは基準値よりも高い。
- 動脈血酸素飽和度〈SaO2〉は100%を超えている。
- 動脈血二酸化炭素分圧〈PaCO2〉は基準値よりも高い。
解答・解説
1.(〇)緊張や恐怖、興奮などの精神的ストレスにより頻呼吸を示す状態を過換気症候群という。頻呼吸によって二酸化炭素の排出量が多くなり、PaCO2の低下や血液pHの上昇がおこり、アルカローシスとなる。
2.(×)ヘマトクリットは血液に占める赤血球の割合であり、過換気症候群による変化は考えにくい。
3.(×)動脈血酸素飽和度が100%を超えることはない。
4.(×)動脈血二酸化炭素分圧〈PaCO2〉は基準値よりも低くなる。
第112回(2023年)
第4問:正常な心臓で心拍出量が減少するのはどれか。
- 心拍数の増加
- 大動脈圧の上昇
- 静脈環流量の増加
- 心筋収縮力の上昇
解答・解説
1.(×)心拍出量は、1回拍出量×心拍数で求められる。心拍数が増加すれば心拍出量は増加する。
2.(〇)大動脈圧の上昇によって左室収縮期圧が上昇し後負荷が増すと、心拍出量は減少する。
3.(×)静脈還流量と心拍出量は等しいため、静脈還流量が増加すれば心拍出量も増える。
4.(×)心筋収縮力の上昇は、心拍出量の増加につながる。
第111回(2022年)
第5問:複数の筋腹が腱で直列につながっている筋はどれか。
- 咬筋
- 上腕二頭筋
- 腹直筋
- 大腿四頭筋
解答・解説
1.(×)咬筋は咀嚼筋のひとつで、頬骨弓から起って下顎骨に付着する。
2.(×)上腕二頭筋は、筋頭が複数に分かれた多頭筋である。<
3.(〇)筋腹が複数回、途中で腱に変わるものを多腹筋と呼び、腹直筋などが該当する。
4.(×)大腿四頭筋は、筋頭が複数に分かれた多頭筋である。
第110回(2021年)
第6問:成人の骨格で線維軟骨結合があるのはどれか。
- 頭蓋冠
- 脊柱
- 寛骨
- 仙骨
解答・解説
1.(×)頭蓋冠は線維性結合である。
2.(〇)線維軟骨結合は椎間円板、恥骨結合などにみられる。
3.(×)成人の寛骨は骨結合である。
4.(×)仙骨は骨結合である。
第109回(2020年)
第7問: B細胞が抗原認識によって分化した抗体産生細胞はどれか。
- マクロファージ
- 形質細胞
- 肥満細胞
- T細胞
解答・解説
1.(×)マクロファージは病原微生物を貪食し、その抗原情報をT細胞に提示する働きをもつ。
2.(〇)B細胞はヘルパーT細胞により活性化されて分裂増殖し、形質細胞となって抗原に特異的な抗体を多く産生する。
3.(×)肥満細胞はI型アレルギー反応に関与し、ヒスタミンを放出する働きをもつ。
4.(×)T細胞はキラーT細胞とヘルパーT細胞がある。キラーT細胞はウイルス感染細胞や移植片を認識・障害し、ヘルパーT細胞は免疫細胞を活性化し、免疫反応を活性化させる働きをもつ。
第111回(2022年)
第7問: B細胞が抗原認識によって分化した抗体産生細胞はどれか。
- マクロファージ
- 形質細胞
- 肥満細胞
- T細胞
解答・解説
1.(×)マクロファージは病原微生物を貪食し、その抗原情報をT細胞に提示する働きをもつ。
2.(〇)B細胞はヘルパーT細胞により活性化されて分裂増殖し、形質細胞となって抗原に特異的な抗体を多く産生する。
3.(×)肥満細胞はI型アレルギー反応に関与し、ヒスタミンを放出する働きをもつ。
4.(×)T細胞はキラーT細胞とヘルパーT細胞がある。キラーT細胞はウイルス感染細胞や移植片を認識・障害し、ヘルパーT細胞は免疫細胞を活性化し、免疫反応を活性化させる働きをもつ。
第111回(2022年)
第8問:リンパの流れで正しいのはどれか。
- 成人の胸管を流れる量は1日約10Lである。
- 右上半身のリンパは胸管に流入する。
- 中枢から末梢への一方向に流れる。
- 筋運動を行うと流量は増加する。
解答・解説
1.(×)リンパ流量は1日約2~4Lである。
2.(×)右上半身は右リンパ本管に流入する。左上半身と下半身は胸管に流入する。
3.(×)末梢から中枢への一方向に流れる。
4.(〇)
筋肉の収縮によって、リンパの流量は増加する。
第112回(2023年)
第9問: 固有心筋の特徴はどれか。
- 平滑筋である。
- 骨格筋よりも不応期が短い。
- 活動電位にプラトー相がみられる。
- 筋層は右心室の方が左心室より厚い。
解答・解説
1.(×)心筋細胞には、固有心筋と特殊心筋があるが、どちらも横紋筋である。
2.(×)不応期は刺激を与えても反応しない時期のこと。心筋は収縮と弛緩を一定のリズムで繰り返すため、骨格筋よりも不応期が長い。
3.(〇)心筋活動電位は、プラトー相(電位が平坦になる相)を有するのが特徴である。
4.(×)心臓の筋層は左心室が最も厚く、右心室の約3倍ある。
第109回(2020年)
第10問: ワクチン接種後の抗体産生について正しいのはどれか。
- ワクチン内の抗原を提示するのは好中球である。
- 抗原に対して最初に産生される抗体はIgAである。
- 抗原に対して血中濃度が最も高くなる抗体はIgMである。
- 同じワクチンを2回接種すると抗原に対する抗体の産生量が増加する。
解答・解説
1.(×)ワクチン内の抗原を提示するのは、樹状細胞、ランゲルハンス細胞、B細胞、マクロファージなどの抗原提示細胞である。
2.(×)抗原に対して最初に産生される抗体はIgMである。
3.(×)抗原に対して血中濃度が最も高くなる抗体はIgGである。
4.(〇)同じワクチンを追加接種することで、抗原に対する抗体の産生量は増加する。
第111回(2022年)
第11問: 成人の睡眠中に分泌が増加するホルモンはどれか。
- アドレナリン
- オキシトシン
- 成長ホルモン
- 甲状腺ホルモン
解答・解説
1.(×) 睡眠中に分泌が増加するホルモンは、成長ホルモンやメラトニン、プロラクチンなどである。
2.(×)
3.(〇)
4.(×)
第110回(2021年)
第12問:生体内でタンパク質が分解され、アミノ酸の代謝が進んで生じたアンモニアは肝臓で( )に変換される。( )に入るのはどれか。
- 尿酸
- 尿素
- 亜硝酸
- 一酸化窒素
解答・解説
1.(×)尿酸はプリン体が肝臓で代謝されたものである。
2.(〇)アンモニアは肝臓の尿素回路で尿素に変換される。
3.(×)亜硝酸はアンモニアがバクテリアによって変換されたものである。水槽のろ過システムなどに利用されている。
4.(×)一酸化窒素は生体内でL-アルギニンから合成される。
第111回(2022年)
第13問:心周期に伴う心臓の変化で、収縮期の初期には心室の容積は変わらずに内圧が上昇していく。このときの心臓で正しいのはどれか。
- 僧房弁は開いている。
- 大動脈弁は開いている。
- 左心室の容積は最小である。
- 左心室の内圧は大動脈圧よりも低い。
解答・解説
1.(×)収縮期には僧帽弁は閉じている。僧帽弁は、心房が収縮して内圧が高まると心室に向かって開く。このとき、心周期は拡張期である。
2.(×)収縮期の初期には左心室圧よりも大動脈圧のほうが高いため、大動脈弁は閉じている。
3.(×)収縮期の初期には左心室の容積は最大となる。
4.(〇)収縮期の初期には左心室の内圧は大動脈圧よりも低い。
第112回(2023年)
第13問: 最も高い照度を必要とするのはどれか。
- 病室
- 手術野
- トイレ
- 病棟の廊下
解答・解説
1.(×)JIS照度基準では、病室は100~200ルクス程度とされている。
2.(〇)JIS照度基準では、手術野は手術台上直径30cmの範囲において無影燈により20,000ルクス以上とされている。
3.(×)JIS照度基準では、トイレは75~150ルクス程度とされている。
4.(×)JIS照度基準では、病棟の廊下は50~100ルクス程度とされている。
第111回(2022年)