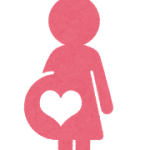大海原に放り出されて
自宅には懐中電灯やろうそくを初め、乾電池、コンロ、レトルト食品など、被災への備えができていた。
自分の運転するワゴン車は、ドアの開閉にコツがいるほど古いのに、段ボール2箱分の防災グッズを詰め込んで「3日間は持ち堪えられる」と豪語していた。
1960年のチリ地震による津波では、この雄勝も被害を受けている。
経験者の1人でもあるこのお年寄りの言葉に、たまたま病院の工事に来ていた作業員らは、病院のすぐ裏山に向かって走り始めた。
だが、鈴木副院長は、平然と答えた。
「患者を置いて逃げられない」
そう言うと、病院の正面玄関から院内へと消えていった。その直後のことだ。病院から道路を挟んですぐ海際に立つ防潮堤を超えて、海水が流れてきた。
まるで風呂のお湯があふれるように、はじめは少しずつ。
やがて大量の海水が道路を埋め、病院の中庭にも流れ込んできた。
駐車していた車が流される。
瞬く間に病院の2階まで埋まっていく。
「患者を屋上に上げるぞ!」
鈴木副院長の大声が飛ぶ。入院患者のシーツの四隅をつかんで屋上に上げようとするが、間に合わない。
職員らは屋上に逃れた。すぐそこに濁流が迫ってくる。
流されてきた家屋が病院とぶつかり「ガチ ャーン」「バリバリ!」という音が聞こえる。
水は足元からひざの高さ、そして腰の高さまで上がってきた。屋上のへりに立った職員たちに、鈴木副院長の声が飛ぶ。
「みんな移れ!」
流されてきた家屋の屋根に飛び移れということだ。みんな、いっせいに屋根をめがけて飛び込むが、滑って波間に引きずり込まれる。
鈴木は何人かの看護師を押し上げようとするが、何人もの白衣姿の看護師が波間に消ええていく。
「サンダルを脱げ!」
屋根に這い上がった鈴木副院長は、今度は、濁流に流される職員らに「タイヤに捕まれ!」などと指示している。
鈴木副院長と看護師の1人を乗せた屋根が、物凄い勢いで引き波に流されていく。
「がんばれよ!」
大きな鈴木副院長の声がだんだん遠ざかっていく。
財布にボロボロの……
津波が病院を襲ったとき、院内にいた入院患者は40人、職員は28人にのぼる。
その全員が流され、一部は雪が降りしきる海原を漂った。
最終的には、助かったのは看護師1人を含む4人だけだ。
病院に籍を置く看護師20人のうち出番だったり、駆けつけたりした看護師7人が亡くなった。
この2日前、「家族が大事だ」と震災時には帰宅を促していた鈴木副院長だが、実際には患者を置いて逃げることなどできなかったのだ。歩けば100メートルほどで避難できる山があったが、病院で患者の命を預る医療従事者の矜持なのか、だれも逃げようとはしなかった。
流されながら助かった看護助手の1人が、迫り来る津波で身の危険を感じ始めていたときに感じたことがある。
「病院にいる限り、私たちは逃げられないんだ」
その病院で患者を死なせてしまった。
震災後、多くの関係者が口を堅く閉ざして、この悲劇を語れなかったのは、そのためだ。
今も負い目となって彼らの上にのしかかる。
(つづく)

夫は子どもたちからもらった「かたたたきけん」や幼い頃の写真を財布に忍ばせていたという。この「やくそく」も、きっと捨てられなかったのだろう
関連著書
『海の見える病院―語れなかった「雄勝」の真実』
辰濃哲郎/著、医薬経済社、本体1,620円+税

あの東日本大震災で、宮城県石巻市郊外の海辺にあった市立雄勝病院が津波に呑み込まれ、患者を含めて64人が亡くなった。人の命を預かる病院で起きた悲劇ゆえ、なかなか実態が見えてこなかった。その職員や家族が重い口を開き、真相を語った。一切の脚色を廃し証言を通じて浮かび上がる悲劇について「何度もページを閉じて、深呼吸をしてからまた読み始めた」「涙なしでは読めない」「医療従事者として覚悟を強いられた」などの評が寄せられる。