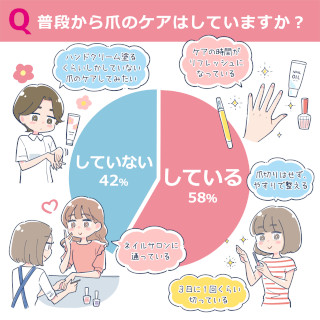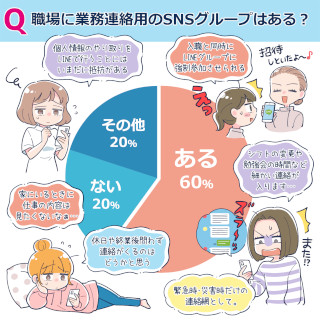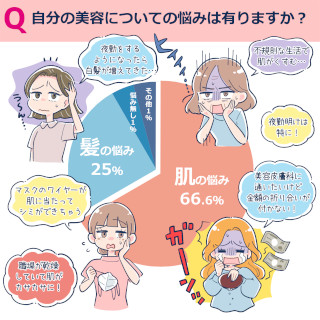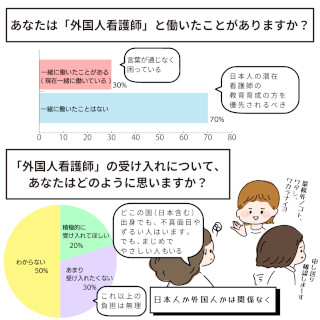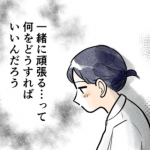2024年11月4日からスタートした1日3問国試ドリルは、月~金で1日3問ずつ配信しています。
このページでは、1日3問国試ドリルで配信した問題のうち、「看護の統合と実践」に該当する問題と解答・解説を掲載します。振り返りにぜひ活用してください。【※毎週更新予定】
第1問:大規模災害発生後2か月が経過し、応急仮設住宅で生活を始めた被災地の住民に出現する可能性が高い健康問題はどれか。
- 慢性疾患の悪化
- 消化器感染症の発症
- 深部静脈血栓症の発症
- 急性ストレス障害の発症
解答・解説
1.(〇)服薬中断、生活環境が変わることによるストレスなどによる慢性疾患の悪化が起こりやすい。
2.(×) 消化器感染症は、トイレなどを共有する避難所生活で発生しやすい。
3.(×) 深部静脈血栓症は、狭い車内やテント内での避難生活で発生しやすい。
4.(×) 急性ストレス障害は、圧倒的な外傷的出来事を目撃または経験して4週間以内に生じる短時間のストレス障害である。
第110回(2021年)
第2問:A君(4歳、男児)は地震による災害のため体育館に両親と避難し、2週間後仮設住宅に移動した。その後1か月経過したころ、A君はわざと机や椅子をガタガタ揺らしながら「地震だ、逃げろ」などと騒いで遊んでいた。母親は仮設住に巡回に来ていた看護師に「Aの遊びにどのように対応したらよいでしょうか」と相談した。看護師の母親への説明で適切なのはどれか。
- 「すぐに児童精神科の医師の診察を受けましょう」
- 「危険な遊びにエスカレートしないよう、やめさせましょう」
- 「避難できたから安心だね、と声をかけながら見守りましょう」
- 「A君に家の手伝いをしてもらい何か役割を担ってもらいましょう」
解答・解説
1.(×)地震ごっこや津波ごっこなどの災害ごっこは、体験を受け入れている過程であり、医師の診察は適切とはいえない。
2.(×)危険が伴う場合は落ち着いて止める必要があるが、エスカレートする可能性を理由にやめさせるのは不適切である。
3.(〇) 子どもに安心感を与える声かけと見守りをするよう説明をすることは適切である。
4.(×)お手伝いなどの役割を担ってもらうこともひとつの方法だが、「Aの遊びにどのように対応したらよいか」という母親の質問への返答としては不適切である。
第113回(2024年)
第3問:災害発生時に行うSTART法によるトリアージで最初に判定を行う項目はどれか。
- 意識
- 呼吸
- 循環
- 歩行
解答・解説
1.(×)START法は一次トリアージの方法で、歩行→自発呼吸→呼吸回数→橈骨動脈触知→簡単な指示、の順に判定を行う。
2.(×)
3.(×)
4. (〇)
第111回(2022年)
第4問:医療法に基づき医療機関が医療の安全を確保する目的で行うのはどれか。
- 医療安全支援センターを設置する。
- 医療安全管理者養成研修を実施する。
- 医療の安全を確保するための指針を策定する。
- 医療安全管理のために必要な研修を2年に1回実施する。
解答・解説
1.(×)医療安全支援センターは、都道府県、保健所を設置する市及び特別区が設置する。
2.(×)医療安全管理者養成研修は、厚生労働省の「医療安全管理者の業務指針および養成のための研修プログラム作成指針」に則り、全日本病院協会や日本看護協会などが実施する。
3.(〇) 医療機関の管理者は、医療の安全を確保するための指針の策定、従業者に対する研修の実施その他の当該病院等における医療の安全を確保するための措置を講じなければならない。
4.(×)医療機関は、1年に2回程度、医療安全管理のための研修を定期的に実施する。
第112回(2023年)
第5問:看護師の特定行為で正しいのはどれか。
- 診療の補助である。
- 医師法に基づいている。
- 手順書は看護師が作成する。
- 特定行為を指示する者に歯科医師は含まれない。
解答・解説
1.(〇)特例行為は診療の補助のうち、定められた38行為をいう。
2.(×) 保健師助産師看護師法に基づく。
3.(×) 手順書は医師・歯科医師が作成する。
4.(×) 特定行為を指示する者には、歯科医師も含まれる。
第109回(2020年)
第6問: 災害拠点病院の説明で正しいのはどれか。
- 国が指定する。
- 災害発生時に指定される。
- 広域搬送の体制を備えている。
- 地域災害拠点病院は各都道府県に1か所設置される。
解答・解説
1.(×)災害拠点病院は、都道府県知事が指定する。
2.(×)災害発生に備えるため、事前に指定される。
3.(〇)傷病者などの受入れ及び搬出を行う広域搬送への対応機能を備えている必要がある。
4.(×)基幹災害拠点病院は原則として各都道府県に1か所設置され、地域災害拠点病院は原則として2次医療圏に1か所設置される。
第111回(2022年)
第7問: 機能別看護方式の説明で正しいのはどれか。
- 勤務帯ごとに各看護師が担当する患者を決めて受け持つ。
- 内容別に分類した看護業務を複数の看護師が分担して実施する。
- 1人の看護師が1人の患者を入院から退院まで継続して受け持つ。
- 患者を複数のグループに分け、各グループを専属の看護師チームが受け持つ。
解答・解説
1.(×)勤務帯ごとに各看護師が担当患者を決めて受け持つという看護方式はない。
2.(〇)機能別看護方式とは、日々の基本的な業務について担当を決めて看護を行う方法である。
3.(×)1人の看護師が1人の患者を継続的に受け持ち、責任をもつ看護方式はプライマリーナーシングである。
4.(×)患者を複数のグループに分け、各グループを専属の看護師チームが受け持つ看護方式は固定チームナーシングである。
第111回(2022年)
第8問: 朝9時に大規模地震が発生した。病棟の患者と職員の安全は確認できた。病棟内の壁や天井に破損はなかったが、病院は、停電によって自家発電装置が作動した。病棟の看護師長が行う対応で適切なのはどれか。
- 災害対策本部を設置する。
- 災害時マニュアルを整備する。
- 隣接する病棟に支援を要請する。
- スタッフに避難経路の安全確認を指示する。
解答・解説
1.(×)災害対策本部は市町村長が設置する。
2.(×)災害時マニュアルの整備は、被災前に整備しておくものである。
3.(×)支援を要請するのではなく、まず安全確認をすることが適切である。
4.(〇)スタッフに避難経路の安全確認の指示を出すのは適切な対応である。
第109回(2020年)
第9問:サイコロジカルファーストエイド(Psychological First Aid:PFA)について正しいのはどれか。
- 活動の原則は、見る、聞く、つなぐである。
- 災害発生から1週間経過してから活動する。
- 被災都道府県からの派遣要請に基づき活動する。
- 苦痛の原因となった出来事を詳細に話すことを促す。
解答・解説
1.(〇)サイコロジカルファーストエイドとは、深刻な危機的出来事に見舞われた人に対して行う、人道的、支持的、実際的な支援のことである。活動の原則は、見る、聞く、つなぐである。
2.(×)サイコロジカルファーストエイドの基本目的は、被災直後から数週間以内に早期支援を提供することである。
3.(×)サイコロジカルファーストエイドは被災都道府県からの派遣要請がなくても、緊急の必要があると認める時には活動を開始できる。
4.(×)苦痛の原因について詳細に話すよう促すことは、更に苦痛を与える可能性がある。サイコロジカルファーストは苦痛を減らし、現在のニーズに対する援助をし、適応的な機能を促進することである。
第113回(2024年)
第10問:国際協力として5歳未満児死亡率の高い地域に1年間派遣されることになった看護師が、派遣される地域の住民に対して行う活動でプライマリヘルスケアの原則に基づいた活動はどれか。
- 高度な治療を目的とした活動
- 医学的研究の遂行を優先した活動
- 派遣先で入手できる資源を利用した活動
- 派遣される専門家チームを中心とする活動
解答・解説
1.(×)プライマリヘルスケアの原則は、①住民の主体的参加、②住民のニーズ指向性、③地域資源の有効活用、④適正な技術、⑤他分野との連携の5つである。5歳未満児死亡率の高い地域において、派遣先で入手できる資源を利用した活動は「地域資源の有効活用」に即している。
2.(×)
3.(〇)
4.(×)
第112回(2023年)
第11問:仙骨部に皮下組織に達する褥瘡がある患者が入院となった。患者は車椅子の利用を主治医に許可されている。この患者に対する多職種で行う褥瘡ケアにおいて、受け持ち看護師が担う役割で適切なのはどれか。
- 薬剤師に外用薬の処方を依頼する。
- 事務職員に汚染ガーゼの廃棄を依頼する。
- 介護職員にドレッシング材の選択を依頼する。
- 理学療法士と車椅子乗車時の除圧方法を検討する。
解答・解説
1.(×)医師法により、薬物の処方は医師が行う。
2.(×)汚染ガーゼは感染のリスクがあり、事務職員に依頼する業務ではない。
3.(×)ドレッシング材の選択は、医師や看護師が褥瘡部分の状態をみて判断する。
4.(〇)車椅子乗車時の除圧方法を理学療法士とともに検討するのは適切である。
第12問:国際機関と事業内容の組合せで正しいのはどれか。
- 国際労働機関〈ILO〉──難民の帰還支援
- 世界保健機関〈WHO〉──保健分野における研究の促進
- 国連人口基金〈UNFPA〉──平和維持活動
- 国連世界食糧計画〈WFP〉──二国間の国際保健医療協力
解答・解説
1.(×)国際労働機関〈ILO〉は、幅広い労働の問題の解決に取り組む国際機関である。難民の帰還支援は国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)が行う。
2.(〇)世界保健機関〈WHO〉は、グローバルな保健問題についてリーダーシップを発揮し、健康に関する研究課題を作成し、規範や基準を設定する国際機関である。
3.(×)国連人口基金は〈UNFPA〉は、国際的な資金によって開発途上国や経済移行諸国に人口関連の支援を行う機関である。平和維持活動は、国連平和維持活動(PKO)が行う。
4.(×)国連世界食糧計画〈WFP〉は、飢餓のない世界を目指して活動する、国連の人道支援機関である。二国間の国際保健医療協力は、国際協力機構(JICA)が行う。
第110回(2021年)
第13問:診療情報について適切なのはどれか。
- 診療情報の開示請求は患者本人に限られる。
- 2類感染症の罹患情報は市区町村長に届け出る。
- 医療者は患者が「知りたくない」と拒否した場合でも病状を説明する。
- 他院へのセカンドオピニオンを希望する患者に診療情報提供書を作成する。
解答・解説
1.(×)診療記録の開示を求められる者は、原則として患者本人とされるが、法定代理人、診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人、患者本人から代理権を与えられた親族及びこれに準ずる者なども開示請求ができる。
2.(×)2類感染症の罹患情報は、最寄りの保健所(地域によっては保健福祉センター、保健環境事務所など)に届け出る。
3.(×)患者には「知る権利」だけでなく「知らないでいる権利」もあるため、「知りたくない」と拒否した場合に病状を説明するのは不適切である。
4.(〇)患者が他院へのセカンドオピニオンを希望した場合には、診療情報提供書を作成するのは適切である。
第113回(2024年)