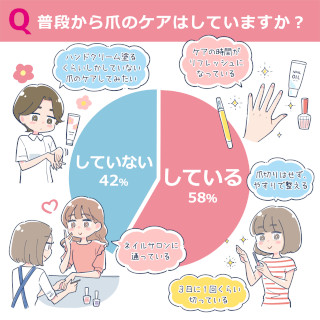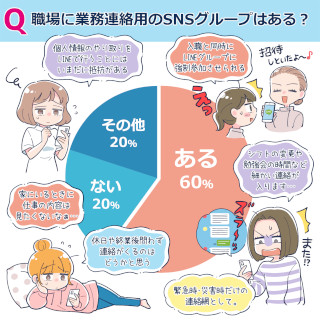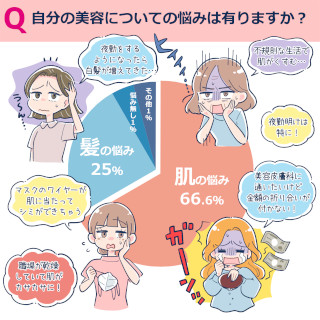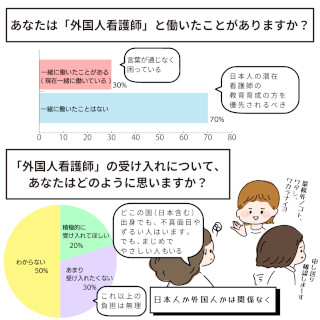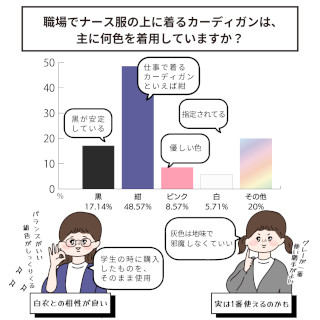2024年11月4日からスタートした1日3問国試ドリルは、月~金で1日3問ずつ配信しています。
このページでは、1日3問国試ドリルで配信した問題のうち、「成人看護学」に該当する問題と解答・解説を掲載します。振り返りにぜひ活用してください。【※毎週更新予定】
第1問:散瞳薬を用いて眼底検査を受ける成人患者への対応で適切なのはどれか。
- 検査中は室内を明るくする。
- 散瞳薬の点眼は検査直前に行う。
- 検査前に緑内障の有無を確認する。
- 検査後1時間で自動車の運転が可能になると説明する。
解答・解説
1.(×) 散瞳すると眼に入る光の量が増えてまぶしく感じるため、室内は暗くする。
2.(×) 散瞳薬は検査の30分前に点眼する。
3.(〇)緑内障患者への散瞳薬の点眼は禁忌である。
4.(×) 散瞳は4~6時間ほど続くため、自動車やバイクなどの運転は危険である。
第109回(2020年)
第2問:Aさん(64歳、男性)は肺炎のため抗菌薬の投与目的で入院となった。治療開始後3日に全身の皮膚、眼瞼結膜および口腔粘膜に紅斑と水疱が出現した。バイタルサインは、体温38.5℃、呼吸数24/分、脈拍80/分、血圧124/80mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉96%(room air)であった。Aさんに出現している症状から考えられる病態はどれか。
- 後天性表皮水疱症
- シェーグレン症候群
- 全身性エリテマトーデス
- スティーブンス・ジョンソン症候群
解答・解説
1.(×) 後天性表皮水疱症は、肘関節の伸側や手足の背側などに水疱がみられる自己免疫疾患である。
2.(×) シェーグレン症候群は、目や口腔内など粘膜の乾燥、関節痛、レイノー現象などがみられる自己免疫疾患である。
3.(×) 全身性エリテマトーデスは、発熱や全身倦怠感、関節炎、蝶型紅斑などがみられる自己免疫疾患である。
4. (〇)スティーヴンス・ジョンソン症候群は、高熱や全身倦怠感などの症状を伴って、口唇・口腔、眼、外陰部などを含む全身に紅斑、びらん、水疱が多発し、表皮の壊死性障害を認める疾患で、薬剤性が多い。
第110回(2021年)
第3問:成人に対する自動体外式除細動器〈AED〉の使用で正しいのはどれか。
- 胸部が濡れている場合は電極パッドを貼る前に拭き取る。
- 電極パッドは左前胸部に並べて貼る。
- 心電図の解析中にも胸骨圧迫を継続する。
- 心拍が再開されたら電極パッドを直ちにはがす。
解答・解説
1.(〇)胸部が濡れている場合、体表でショートしてしまい、心臓に十分な電流が届かない可能性があるため、電極パッドを貼る前に水分を拭き取る。
2.(×)電極パッドは右前胸部と左前胸部に貼る。
3.(×)心電図の解析中は傷病者の体に触れないようにする。
4.(×)心拍再開後も電極パッドははがさず、AEDの電源も入れたままにする。
第112回(2023年)
第4問:Aさん(54歳、女性)は甲状腺機能亢進症と診断され、放射性ヨウ素内用療法を受けることとなった。看護師の説明で正しいのはどれか。
- 「治療前1週間は海藻類を摂取しないでください」
- 「治療中の体を固定します」
- 「治療後の副作用に脱毛があります」
- 「治療後1週間は生野菜を摂取しないでください」
解答・解説
1.(〇)放射線ヨウ素内用療法では、治療の1~2週間前からヨウ素制限を行う。海藻類や魚介類が該当する。
2.(×)行動制限の必要はないが、放射性ヨウ素カプセルを内服後、1~3週間は子どもや妊婦との接触を控える必要がある。
3.(×)脱毛の副作用はない。頸部や唾液腺(耳下腺・顎下腺)の腫脹、血液成分の減少がみられることがある。
4.(×)生野菜の摂取制限はない。
第111回(2022年)
第5問:成人のがん患者が痛みの程度を数値で回答するスケールはどれか。
- フェイススケール
- NRS
- VAS
- VRS
解答・解説
1.(×) フェイススケールは、患者の表情によって痛みの程度を判定する方法である。主に高齢者や小児に利用される。
2.(〇)NRS(Numerical Rating Scale)は、痛みがない状態を0、想像できる最大の痛みを10として、11段階で痛みの程度を数値で回答するスケールである。成人のがん患者に痛みの程度を数値で答えてもらうのに適切な方法である。
3.(×)VAS(Visual Analogue Scale)は、長さ10cmの黒い線の左端を痛みがない状態、右端を想像できる最大の痛みとして示し、現在の痛みがどの程度かを指し示してもらうスケールである。
4.(×)VRS(Verbal Rating Scale)は、痛みなし・少し痛い・痛い・かなり痛い・耐えられないほど痛いなど、痛みの強さを表す言葉を並べて、痛みの程度に合う言葉を選んでもらう段階的スケールである。
第113回(2024年)
第6問:Aさん(47歳、男性、会社員)は、尿管結石による疝痛発作で入院した。入院翌日、自然に拝石され、疼痛は消失したものの、結石が残存している。入院前はほぼ毎日、飲酒を伴う外食をしていた。Aさんへの退院指導で適切なのはどれか。
- 「シュウ酸を多く含む食品を摂取しましょう」
- 「1日2L程度の水分を摂取しましょう」
- 「拝石までは安静にしましょう」
- 「飲酒量に制限はありません」
解答・解説
1.(×)尿路結石には、シュウ酸カルシウム結石と尿酸結石があり、シュウ酸、プリン体(代謝されると尿酸になる)を含む食品は避けるよう指導するのが適切である。シュウ酸はホウレン草、タケノコ、チョコレートに、プリン体はビール、魚の干物、シイタケなどに多く含まれている。
2.(〇)水分を多く摂取して尿量を増やすことで、結石の排出が促進される。1日2L程度の水分摂取を促すことは適切である。
3.(×)排石には運動が効果的なため、安静を促すのは不適切である。
4.(×)飲酒は利尿作用によって脱水状態となり、結石のリスクを上げる。飲酒量は減らしたほうがよいため、飲酒量に制限がないと伝えるのは不適切である。
第113回(2024年)
第7問:広汎子宮全摘出術を受けた患者への退院後の生活に関する説明で正しいのはどれか。
- 「術後2週から性交は可能です」
- 「定期的に排尿を試みてください」
- 「調理のときは手袋をしてください」
- 「退院当日から浴槽の湯に浸かることができます」
解答・解説
1.(×)術後の経過や病理診断の結果などによって、性交が可能になる時期は異なる。
2.(〇)広汎子宮全摘出術は術後に排尿障害を起こしやすく、定期的に排尿を試みるのは適切である。
3.(×)乳がんのリンパ節切除後の場合、手がリンパ浮腫を起こすため、調理時に調理用手袋が勧められるが、広汎子宮全摘出術では下肢や下腹部にリンパ浮腫が起きるため、手袋は必要ない。
4.(×)医師の許可が出るまではシャワー浴のみとなる。
第112回(2023年)
第8問:血中濃度の測定にあたり食事の影響を考慮すべきホルモンはどれか。
- グルカゴン
- メラトニン
- コルチゾール
- バゾプレシン
解答・解説
1.(〇)血漿グルカゴン濃度は食事による影響を受ける。
2.(×)メラトニンは外界の光刺激によって分泌量が変化する。
3.(×)コルチゾールは早朝高値・夜間低値の生理的日内変動を示すほか、運動やストレスなどによる影響を受ける。
4.(×)バゾプレシンは血圧の低下、血症浸透圧の上昇、痛みやストレス、薬剤などによる影響を受ける。
第111回(2022年)
第9問: 重度の肝硬変(cirrhosis)で基準値よりも低い値を示す血液検査項目はどれか。
- 血清アルブミン〈Alb〉
- 血清ビリルビン〈Bil〉
- 血中アンモニア〈NH3〉
- プロトロンビン時間〈PT〉
解答・解説
1.(〇)血清アルブミンは肝臓で作られるたんぱく質の代表で、重度の肝硬変では基準値よりも低下する。
2.(×)血清ビリルビンは黄疸を示す値で、重度の肝硬変では基準値よりも上昇する。
3.(×)血中アンモニアは肝臓で分解されるため、重度の肝硬変では基準値よりも上昇する。
4.(×)プロトロンビン時間は血液の凝固時間を表し、重度の肝硬変では延長する。
第112回(2023年)
第10問:肝動脈塞栓術(TAE)の適応となる疾患はどれか。
- 脂肪肝
- 急性A型肝炎
- 肝細胞癌(HCC)
- アメーバ性肝膿瘍
解答・解説
1.(×)脂肪肝は肝臓に中性脂肪が溜まった状態である。食事療法・運動療法の継続が必要。
2.(×)急性A型肝炎はA型肝炎ウイルスによる感染症である。特効薬はないため、安静と食事療法を行い、重症化や劇症化の有無を経過観察する。
3.(〇)肝動脈塞栓術(TAE)は、がん細胞に酸素や栄養を供給している肝動脈を塞ぎ、肝細胞がんを選択的に壊死させる方法である。
4.(×)アメーバ性肝膿瘍は、アメーバが腸管から門脈血流に侵入し、肝臓に膿瘍をつくった状態。治療として、メトロニダゾール(フラジール ®)やパロモマイシン(アメパロモ ®)の投与が行われる。
第109回(2020年)
第11問:Aさん(63歳、男性)は3年前からpulmonary emphysema肺気腫で定期受診を続けてきた。最近、歩行時の息切れが強くなってきたことを自覚し、心配になったため受診した。受診時、呼吸数は34/分で、口唇のチアノーゼがみられた。Aさんについて正しいのはどれか。
- 1回換気量が増加している。
- 呼気よりも吸気を促すと効果的である。
- 経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉は上昇している。
- 病状が進行すると動脈血二酸化炭素分圧〈PaCO2〉が上昇する。
解答・解説
1.(×)肺気腫では、1回換気量の増加が制限され、歩行時や労作時の息切れの原因となる。
2.(×)肺気腫では勢いよく呼気ができず、呼気時間が延長する。口をすぼめて長く呼気をする口すぼめ呼吸が勧められる。
3.(×)運動時の息切れ、頻呼吸と口唇のチアノーゼが認められており、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉の低下が考えられる。
4.(〇)肺気腫は進行に伴い、PaO2の低下、PaCO2の増加がみられる。
第111回(2022年)
第12問: うっ血性心不全が疑われる患者が救急外来を受診した。その際、12誘導心電図、胸部エックス線検査に加えて行われる優先度が高い検査はどれか。
- 冠動脈CT検査
- 心臓超音波検査
- 心筋シンチグラム
- 心臓カテーテル検査
解答・解説
1.(×)冠動脈CT検査は、冠動脈の狭窄部位を確認するための検査で、狭心症や心筋梗塞の診断に用いられる。うっ血性心不全の原因は虚血性心疾患だけではないため、優先度は低い。
2.(〇)うっ血性心不全は、何らかの要因により心機能の低下したことで、全身の循環系に血液が停滞した状態である。うっ血性心不全の原因として、虚血性心疾患、心筋症、弁膜症などがあり、鑑別診断が必要である。心臓超音波検査は、これらの鑑別に有用な検査方法である。
3.(×)心筋シンチグラムは、心筋へ流れる血液の量や心筋の機能を画像化したもので、狭心症や心筋梗塞の診断に用いられる。うっ血性心不全の原因は虚血性心疾患だけではないため、優先度は低い。
4.(×)心臓カテーテル検査は、カテーテルを心臓まで挿入し、心内圧の測定や冠動脈や心臓の血行動態の評価を行うための検査である。X線撮影置を用いて造影を行う必要があり、心臓超音波検査を行うほうが優先度は高い。
第113回(2024年)
第13問: Aさん(34歳、女性)は、気管支喘息で定期的に通院をしている。朝から喘息発作があり呼吸困難が生じたため、救急外来を受診した。経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉95%、動脈血液ガス分析(room air)で動脈血酸素分圧〈PaO2〉90Torr、動脈血二酸化炭素分圧〈PaCO2〉55Torr、pH7.30、HCO3-25mEq/Lであった。Aさんの状態で考えられるのはどれか。
- 呼吸性アシドーシス
- 呼吸性アルカローシス
- 代謝性アシドーシス
- 代謝性アルカローシス
解答・解説
1.(〇)動脈血pHは7.35~7.45が正常である。AさんはpH7.30と低下しており、アシドーシスの状態である。また、PaCO2は35~45Torrが正常であるがAさんは55Torrと高い。呼吸性アシドーシスと考えられる。気管支喘息や肺気腫などの閉塞性換気障害が原因となる。
2.(×)呼吸性アルカローシスは、pHが7.45以上でPaCO2が低い状態である。過換気症候群などが原因となる。
3.(×)代謝性アシドーシスは、pHが7.35以下でHCO3-が低い状態である。
4.(×)代謝性アルカローシスは、pHが7.45以上でHCO3-が高い状態である。
第110回(2021年)